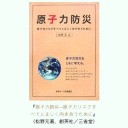『寝る子は脳もよく育つ 東北大チーム
睡眠時間の長い子どもほど、記憶や感情に関わる脳の部位「海馬」の体積が大きかったことを、東北大の滝靖之教授らの研究チームが突き止めた。18日から名古屋市で開催の日本神経科学大会で発表する。
うつ病や高齢者のアルツハイマー病患者で、海馬の体積が小さいことが分かっており、滝教授は「子どものころから十分な睡眠をとり生活習慣を改善することで、生涯にわたって健康な脳を築ける可能性がある」としている。
研究チームは2008年からの4年間で、健康な5~18歳の290人の平日の睡眠時間と、海馬の体積を調べた。睡眠が10時間以上の子どもは6時間の子どもより、海馬の体積が1割程度大きいことが判明した。』
そうは言っても子供に戻る事はできないから,高齢者の増加に比例して今後すます増えるであろう認知症の患者さんはどうにもならないだろう.
子どもにしても最近の子ども達は大人の都合で就眠時刻が遅くなっているようだから,幼児期に脳の成長に十分な睡眠時間がとれるかどうかは親次第だろう.それに小学生も高学年になると塾から帰ってから学校の宿題をやったりして寝るのが午後10時以降という子もめずらしくないようだ.
わが家でも小学5年生までは夜9時には就眠していたが,6年生からは徐々に遅らせて中学1年生になってからは夜10時30分が就眠時刻になった.それでも午前6時30分には起きてもらうから睡眠時間は8時間.私も中学2年生まではこれくらいは寝ていた記憶がある.
中学3年生にもなれば受験勉強でこんなには寝ていられなくなるのだろうが,娘の話では中学1年生から午後12時まで勉強している子が結構いるようなので,今からそんなに勉強しなければならない子ども達がかわいそうな気がしてしまう.最近の中学校は勉強以外にも色々な事を宿題にしてくれるので子供の時間の余裕がなくなっているように思う.
ゆとり教育の反動なのだろうが,人間の能力には限界があるし知識を詰め込んでも頭は良くはならないから,子どもの人間性や思考能力を高めることを考えて欲しいと思うが,いじめ問題を見てもわかるように現場の教師達にはそんなことを考える余裕も能力もないのだろう.
勉強や委員会の仕事だけで毎日疲れてしまっている娘をみているとあまり頑張れというわけにもいかないし,かといって勉強で落ちこぼれるのも困るので何と言っていいかわからず,せめて休日だけでもゆっくり寝かせておいてあげたいと思うのは私だけだろうか.
睡眠時間の長い子どもほど、記憶や感情に関わる脳の部位「海馬」の体積が大きかったことを、東北大の滝靖之教授らの研究チームが突き止めた。18日から名古屋市で開催の日本神経科学大会で発表する。
うつ病や高齢者のアルツハイマー病患者で、海馬の体積が小さいことが分かっており、滝教授は「子どものころから十分な睡眠をとり生活習慣を改善することで、生涯にわたって健康な脳を築ける可能性がある」としている。
研究チームは2008年からの4年間で、健康な5~18歳の290人の平日の睡眠時間と、海馬の体積を調べた。睡眠が10時間以上の子どもは6時間の子どもより、海馬の体積が1割程度大きいことが判明した。』
そうは言っても子供に戻る事はできないから,高齢者の増加に比例して今後すます増えるであろう認知症の患者さんはどうにもならないだろう.
子どもにしても最近の子ども達は大人の都合で就眠時刻が遅くなっているようだから,幼児期に脳の成長に十分な睡眠時間がとれるかどうかは親次第だろう.それに小学生も高学年になると塾から帰ってから学校の宿題をやったりして寝るのが午後10時以降という子もめずらしくないようだ.
わが家でも小学5年生までは夜9時には就眠していたが,6年生からは徐々に遅らせて中学1年生になってからは夜10時30分が就眠時刻になった.それでも午前6時30分には起きてもらうから睡眠時間は8時間.私も中学2年生まではこれくらいは寝ていた記憶がある.
中学3年生にもなれば受験勉強でこんなには寝ていられなくなるのだろうが,娘の話では中学1年生から午後12時まで勉強している子が結構いるようなので,今からそんなに勉強しなければならない子ども達がかわいそうな気がしてしまう.最近の中学校は勉強以外にも色々な事を宿題にしてくれるので子供の時間の余裕がなくなっているように思う.
ゆとり教育の反動なのだろうが,人間の能力には限界があるし知識を詰め込んでも頭は良くはならないから,子どもの人間性や思考能力を高めることを考えて欲しいと思うが,いじめ問題を見てもわかるように現場の教師達にはそんなことを考える余裕も能力もないのだろう.
勉強や委員会の仕事だけで毎日疲れてしまっている娘をみているとあまり頑張れというわけにもいかないし,かといって勉強で落ちこぼれるのも困るので何と言っていいかわからず,せめて休日だけでもゆっくり寝かせておいてあげたいと思うのは私だけだろうか.
正確な情報を得るのは悪くない
2012年8月29日 社会の問題 コメント (1)『妊婦の血液でダウン症診断 5施設で9月以降導入 中絶大幅増の懸念も
妊婦の血液を調べるだけで、胎児にダウン症などの染色体異常があるかどうかがほぼ確実に分かる新しい出生前診断を、国立成育医療研究センター(東京)や昭和大(同)が9月にも導入する方針であることが29日、分かった。
新しい診断法は、妊婦の腹部に細い針を刺す「羊水穿(せん)刺(し)」で羊水を採取する従来の方法に比べて安全にできるが、簡単な検査のため、異常が発見された際の人工妊娠中絶が大幅に増える懸念もある。米国では昨年から実施されており、国内にも導入の動きがあったことなどから、日本産科婦人科学会は生命の尊厳を尊重したルール作りが必要と判断。専門医やカウンセラーなど体制が整備された医療機関で先行的に行い、検討する必要があるとした。
導入を検討している病院の医師らは31日に研究組織を立ち上げ、検査を行う際の共通のルールを作る。
ほかに東京慈恵会医大、東大、横浜市立大などで導入を検討。高齢出産だったり、以前にダウン症の子供を出産していたりするなど、染色体異常のリスクが高い妊婦で検査希望者が対象になる。保険がきかず、費用は20万円程度になる。
検査は妊娠10週目以降から可能で、妊婦の血液中に含まれるわずかな胎児のDNA型を調べ、99%の精度で異常が分かるという。
日本産科婦人科学会副理事長の岡井崇昭和大教授は「これまでに比べて検査時のリスクが格段に小さくなるが、乱用されれば問題も出てくる。どう行っていけばいいか、しっかり検討したい」としている。
一方、日本ダウン症協会の水戸川真由美理事は「出生前診断が胎児のふるい分けとして一般化したり、安易に行われることは断固反対。検査に対する基本的な考え方をしっかりと明示してほしい」と述べた。』
これで高齢出産のリスクが一つ確実に減ることになるのだろう.いずれ同様に他の遺伝子異常や遺伝病の診断も可能になるのだろうから,これがその始まりになるのは間違いない.
母体へのリスクがほぼ0で出生前診断ができるのに「乱用されれば問題」とか「安易に行われることは断固反対」という意見が出て来る事が私には理解出来ない.異常があるかないかを知った上で生むか生まないかは妊婦さん自身が決めればいいだけのことだろう.
そもそも現状でも親の勝手な都合で中絶は行われているのだから,ダウン症がわかったからといって中絶大幅増なんてことが起こるとは考えにくいし,体外受精で他人に子供を産んでもらう人までいるわが国でそんなことを議論するのは馬鹿げているようにさえ思う.
『「産むことに迷いない」胎児に障害の可能性 東尾理子さんに聞く
もし、おなかの赤ちゃんに障害の可能性があったら...。誰もが思い悩む重いテーマだ。俳優・石田純一さん(58)の妻で、妊娠中のプロゴルファー東尾理子さん (36)が「胎児にダウン症の可能性がある」と診断されたことを6月にブログで公表した。出産を11月に控え「産むことに迷いはない」と言い切る東尾さんに、不妊治療や出生前診断への思いを聞いた。
―不妊治療による待望の妊娠だったそうですね。
「2009年12月に結婚し、子どもが欲しかったので医師に勧められたタイミング法(予測した排卵日に性交渉する方法)を試しました。それでも授からず、昨年の初めごろから(採取した精子を子宮内に入れる)人工授精を6回、さらに(精子、卵子ともに取り出して、受精させてから子宮内に戻す)体外受精に切り替え、3回目で妊娠しました」
―治療中のつらさは。
「人工授精は平気でしたが、体外受精は排卵誘発剤や抑制剤を毎日自分でおなかやお尻に注射します。おなかはぱんぱんに張って苦しく、痛みで全然動けませんでした」
―精神的には。
「大丈夫でした。できるものはできる、できないものはできない。自分でコントロールできることではなく、怒っても悲しんでも仕方がない。できることを精いっぱいやるだけでした」
―3月、妊娠検査薬で陽性と出た結果を直後にブログで公表しました。流産の恐れがまだ残る時期でしたが。
「実は、流産は15~20%と高い確率で起きるという事実や、初期の流産は母体の責任ではなく受精卵の運命なのだということを、不妊治療を始めてから学びました。知らないのは普段耳にしないから。たとえ流産したとしても『ごく普通にあることだよ』と発信することに意味があると思い、どんな結果も受け止める覚悟で公表しました」
―母体から採血し、胎児の染色体異常の可能性を調べる母体血清マーカー検査(クアトロテスト)を受けましたね。なぜ検査を。
「障害の有無を確かめたかったわけではなく、いろいろある血液検査の一つとの認識でした。検査の結果、82分の1の確率で胎児にダウン症の可能性があると診断されました」
―結果を聞いてどうでしたか。
「年齢の割には高い確率との説明でしたが『この子をおろす選択肢はない。絶対に産む』と強く感じました。検査した時期はつわりで苦しいだけ。でも結果が出たころには胎動も始まり、母になる自覚ができました。どんな赤ちゃんでも幸せ。一緒に暮らしていこうと。(障害の有無が分かる確度が高い)羊水検査は考えませんでした」
―6月にブログで結果を公表しました。批判もあったようですが。
「障害は特別なことではないし、物議を醸すとは思ってもいませんでした。いろんな考えがあると勉強になりました」
―若い人たちに伝えたいことは。
「技術の進歩で『いつでも産める』という間違った安心感が広がっていますが、高齢になれば妊娠率は下がり、流産率や障害の率は上がります。振り返ると避妊の方法は習っても、こうした事実は誰も教えてくれませんでした。仮に私が20代でこの事実を知っていたとしてもゴルフを優先していたでしょう。でも、何を犠牲にして今の人生を歩んでいるか、随分と意味が違ったはずです。時間を無駄にしないためにも、体の仕組みをしっかり理解した上で、人生設計を立ててほしいです」』
まず「技術の進歩で『いつでも産める』という間違った安心感が広がる」ことのないように教育し,生命に対する正しい認識や倫理観を持ってもらう事からはじめるべきだろう.
妊婦の血液を調べるだけで、胎児にダウン症などの染色体異常があるかどうかがほぼ確実に分かる新しい出生前診断を、国立成育医療研究センター(東京)や昭和大(同)が9月にも導入する方針であることが29日、分かった。
新しい診断法は、妊婦の腹部に細い針を刺す「羊水穿(せん)刺(し)」で羊水を採取する従来の方法に比べて安全にできるが、簡単な検査のため、異常が発見された際の人工妊娠中絶が大幅に増える懸念もある。米国では昨年から実施されており、国内にも導入の動きがあったことなどから、日本産科婦人科学会は生命の尊厳を尊重したルール作りが必要と判断。専門医やカウンセラーなど体制が整備された医療機関で先行的に行い、検討する必要があるとした。
導入を検討している病院の医師らは31日に研究組織を立ち上げ、検査を行う際の共通のルールを作る。
ほかに東京慈恵会医大、東大、横浜市立大などで導入を検討。高齢出産だったり、以前にダウン症の子供を出産していたりするなど、染色体異常のリスクが高い妊婦で検査希望者が対象になる。保険がきかず、費用は20万円程度になる。
検査は妊娠10週目以降から可能で、妊婦の血液中に含まれるわずかな胎児のDNA型を調べ、99%の精度で異常が分かるという。
日本産科婦人科学会副理事長の岡井崇昭和大教授は「これまでに比べて検査時のリスクが格段に小さくなるが、乱用されれば問題も出てくる。どう行っていけばいいか、しっかり検討したい」としている。
一方、日本ダウン症協会の水戸川真由美理事は「出生前診断が胎児のふるい分けとして一般化したり、安易に行われることは断固反対。検査に対する基本的な考え方をしっかりと明示してほしい」と述べた。』
これで高齢出産のリスクが一つ確実に減ることになるのだろう.いずれ同様に他の遺伝子異常や遺伝病の診断も可能になるのだろうから,これがその始まりになるのは間違いない.
母体へのリスクがほぼ0で出生前診断ができるのに「乱用されれば問題」とか「安易に行われることは断固反対」という意見が出て来る事が私には理解出来ない.異常があるかないかを知った上で生むか生まないかは妊婦さん自身が決めればいいだけのことだろう.
そもそも現状でも親の勝手な都合で中絶は行われているのだから,ダウン症がわかったからといって中絶大幅増なんてことが起こるとは考えにくいし,体外受精で他人に子供を産んでもらう人までいるわが国でそんなことを議論するのは馬鹿げているようにさえ思う.
『「産むことに迷いない」胎児に障害の可能性 東尾理子さんに聞く
もし、おなかの赤ちゃんに障害の可能性があったら...。誰もが思い悩む重いテーマだ。俳優・石田純一さん(58)の妻で、妊娠中のプロゴルファー東尾理子さん (36)が「胎児にダウン症の可能性がある」と診断されたことを6月にブログで公表した。出産を11月に控え「産むことに迷いはない」と言い切る東尾さんに、不妊治療や出生前診断への思いを聞いた。
―不妊治療による待望の妊娠だったそうですね。
「2009年12月に結婚し、子どもが欲しかったので医師に勧められたタイミング法(予測した排卵日に性交渉する方法)を試しました。それでも授からず、昨年の初めごろから(採取した精子を子宮内に入れる)人工授精を6回、さらに(精子、卵子ともに取り出して、受精させてから子宮内に戻す)体外受精に切り替え、3回目で妊娠しました」
―治療中のつらさは。
「人工授精は平気でしたが、体外受精は排卵誘発剤や抑制剤を毎日自分でおなかやお尻に注射します。おなかはぱんぱんに張って苦しく、痛みで全然動けませんでした」
―精神的には。
「大丈夫でした。できるものはできる、できないものはできない。自分でコントロールできることではなく、怒っても悲しんでも仕方がない。できることを精いっぱいやるだけでした」
―3月、妊娠検査薬で陽性と出た結果を直後にブログで公表しました。流産の恐れがまだ残る時期でしたが。
「実は、流産は15~20%と高い確率で起きるという事実や、初期の流産は母体の責任ではなく受精卵の運命なのだということを、不妊治療を始めてから学びました。知らないのは普段耳にしないから。たとえ流産したとしても『ごく普通にあることだよ』と発信することに意味があると思い、どんな結果も受け止める覚悟で公表しました」
―母体から採血し、胎児の染色体異常の可能性を調べる母体血清マーカー検査(クアトロテスト)を受けましたね。なぜ検査を。
「障害の有無を確かめたかったわけではなく、いろいろある血液検査の一つとの認識でした。検査の結果、82分の1の確率で胎児にダウン症の可能性があると診断されました」
―結果を聞いてどうでしたか。
「年齢の割には高い確率との説明でしたが『この子をおろす選択肢はない。絶対に産む』と強く感じました。検査した時期はつわりで苦しいだけ。でも結果が出たころには胎動も始まり、母になる自覚ができました。どんな赤ちゃんでも幸せ。一緒に暮らしていこうと。(障害の有無が分かる確度が高い)羊水検査は考えませんでした」
―6月にブログで結果を公表しました。批判もあったようですが。
「障害は特別なことではないし、物議を醸すとは思ってもいませんでした。いろんな考えがあると勉強になりました」
―若い人たちに伝えたいことは。
「技術の進歩で『いつでも産める』という間違った安心感が広がっていますが、高齢になれば妊娠率は下がり、流産率や障害の率は上がります。振り返ると避妊の方法は習っても、こうした事実は誰も教えてくれませんでした。仮に私が20代でこの事実を知っていたとしてもゴルフを優先していたでしょう。でも、何を犠牲にして今の人生を歩んでいるか、随分と意味が違ったはずです。時間を無駄にしないためにも、体の仕組みをしっかり理解した上で、人生設計を立ててほしいです」』
まず「技術の進歩で『いつでも産める』という間違った安心感が広がる」ことのないように教育し,生命に対する正しい認識や倫理観を持ってもらう事からはじめるべきだろう.
『「根性焼き」は合意による行為と認識…学校側
仙台市の私立高校の男子生徒(16)が、同級生からたばこの火を腕に押しつけられる「根性焼き」などのいじめを受けたとして仙台東署に被害届を出した問題で、生徒が通う学校の教頭は7日、読売新聞の取材に応じ、「いじめの可能性を否定せず再調査する」と話した。
「他の生徒に動揺を与える」として生徒側に求めていた自主退学は保留扱いとした。
学校の説明では、生徒の保護者からいじめの相談を受け、7月中旬に校内に調査委員会を設置。いじめたとされる生徒に話を聞いたところ、被害生徒が自分でたばこの火を腕に押しつけたなどと説明を受けた。被害生徒も自分から頼んだと説明したとして、やけどは「自傷行為」、または「合意による」と認識したという。
その後、被害生徒が、やけどはいじめによるものと申し出たため、学校側は他の生徒から話を聞くなどしたが、いじめとは認めず、生徒側に今月6日までに自主退学するよう求めたという。学校側は、自主退学に応じなければ退学処分にするとしていたが、被害届が出された6日に行われた保護者との話し合いで、「保護者が納得していない」などとして、再調査と退学処分の保留を決めた。
学校側は、いじめたとされる同級生が7月31日付で自主退学したことも明らかにした。』
いじめによる傷害事件を闇から闇へ葬り去る事を考えた学校も,警察に被害届が出されたことで事件が公になってしまったので仕方なく再調査する事にしたということだろう.
いじめがあることが世間にバレると学校の評判にかかわるからもみ消しを計るのに,加害者と被害者を両方とも自主退学するように仕向けるとは教育者のやることではないが,この事件が明るみに出た事で学校の評価は最低になるだろう.
今の世の中は情報の拡散スピードが昔とは比べ物にならないから,こういう不適切なことをやってそれを隠し通せるわけなどないのだが,そういうことがわからない人が世の中にはまだたくさんいるようだ.
学校に限らず世の中でいじめにあっている人たちもこれからはどんどん情報公開すればいいのではないだろうか.もちろん犯罪行為の被害を受けた場合は警察に相談するのが一番いいだろう.学校の先生なんてもはや信用するに値しないということはニュースを見れば明らかだ.
学校に限らず会社や役所の事なかれ主義にはもう嫌気がさしているから,真実から目を背けた挙げ句に隠蔽するような組織にはきちんと社会的責任を取ってもらうのには大賛成だ.
仙台市の私立高校の男子生徒(16)が、同級生からたばこの火を腕に押しつけられる「根性焼き」などのいじめを受けたとして仙台東署に被害届を出した問題で、生徒が通う学校の教頭は7日、読売新聞の取材に応じ、「いじめの可能性を否定せず再調査する」と話した。
「他の生徒に動揺を与える」として生徒側に求めていた自主退学は保留扱いとした。
学校の説明では、生徒の保護者からいじめの相談を受け、7月中旬に校内に調査委員会を設置。いじめたとされる生徒に話を聞いたところ、被害生徒が自分でたばこの火を腕に押しつけたなどと説明を受けた。被害生徒も自分から頼んだと説明したとして、やけどは「自傷行為」、または「合意による」と認識したという。
その後、被害生徒が、やけどはいじめによるものと申し出たため、学校側は他の生徒から話を聞くなどしたが、いじめとは認めず、生徒側に今月6日までに自主退学するよう求めたという。学校側は、自主退学に応じなければ退学処分にするとしていたが、被害届が出された6日に行われた保護者との話し合いで、「保護者が納得していない」などとして、再調査と退学処分の保留を決めた。
学校側は、いじめたとされる同級生が7月31日付で自主退学したことも明らかにした。』
いじめによる傷害事件を闇から闇へ葬り去る事を考えた学校も,警察に被害届が出されたことで事件が公になってしまったので仕方なく再調査する事にしたということだろう.
いじめがあることが世間にバレると学校の評判にかかわるからもみ消しを計るのに,加害者と被害者を両方とも自主退学するように仕向けるとは教育者のやることではないが,この事件が明るみに出た事で学校の評価は最低になるだろう.
今の世の中は情報の拡散スピードが昔とは比べ物にならないから,こういう不適切なことをやってそれを隠し通せるわけなどないのだが,そういうことがわからない人が世の中にはまだたくさんいるようだ.
学校に限らず世の中でいじめにあっている人たちもこれからはどんどん情報公開すればいいのではないだろうか.もちろん犯罪行為の被害を受けた場合は警察に相談するのが一番いいだろう.学校の先生なんてもはや信用するに値しないということはニュースを見れば明らかだ.
学校に限らず会社や役所の事なかれ主義にはもう嫌気がさしているから,真実から目を背けた挙げ句に隠蔽するような組織にはきちんと社会的責任を取ってもらうのには大賛成だ.
防衛相のはスタンドプレイ
2012年8月4日 社会の問題『オスプレイ防衛相発言に沖縄反発 「個人的な感想」
米軍の新型輸送機MV22オスプレイに米国で試乗した森本敏防衛相が「想像以上に飛行が安定していた」との感想を述べたことについて、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)への配備に反対する沖縄県では4日、「個人的な感想にすぎない」と反発の声が上がった。
県幹部は「防衛相が乗っても県民が安心する状況になっていない」と不快感を示した。
普天間飛行場の米軍機の騒音差し止めなどを国に求めている「普天間爆音訴訟団」の高橋年男事務局長は「過酷な条件での試乗ではなく、安全性の証明にはならない。県民だましのパフォーマンスだ」とあきれた様子で話した。
普天間飛行場の移設先、同県名護市辺野古で抗議活動を続けている安次富浩(あしとみ・ひろし)さんは「試乗はセレモニーで、安定していたと言われても信用できない。安全性を証明したいなら、防衛相専用機にしたらいい」と皮肉った。
防衛相の試乗に対し、仲井真弘多知事も3日に「防衛相はテストパイロットでもないんだし、何か意味があるのか。よく分からない」と記者団に疑問を呈していた。』
食の安全性を問われれば試食してみせるのが政治家の仕事らしいから,飛行機の安全性が問われれば試乗してみせるというのもその延長線上の思考なのだろう。こういう水平思考しかできない政治家も十分危険だが,オスプレイの問題は水平飛行モードから垂直降下モードに切り替わる時の安定性だ.
砂漠の基地で運用するならまだしも,墜落率の高い飛行機をわざわざ住宅地の近くで運用しようというのだから,ヘリコプターに墜落された地元が猛反対するのも当然だろう.それをこんな意味の無いパフォーマンスをした挙げ句に「想像以上に飛行が安定していた」との感想を述べるのというのだからあきれたものだ.
まともにコメントするのもばからしいから「安全性を証明したいなら、防衛相専用機にしたらいい」と言った安次富浩(あしとみ・ひろし)さんに座布団一枚あげたいと思う.
米軍の新型輸送機MV22オスプレイに米国で試乗した森本敏防衛相が「想像以上に飛行が安定していた」との感想を述べたことについて、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)への配備に反対する沖縄県では4日、「個人的な感想にすぎない」と反発の声が上がった。
県幹部は「防衛相が乗っても県民が安心する状況になっていない」と不快感を示した。
普天間飛行場の米軍機の騒音差し止めなどを国に求めている「普天間爆音訴訟団」の高橋年男事務局長は「過酷な条件での試乗ではなく、安全性の証明にはならない。県民だましのパフォーマンスだ」とあきれた様子で話した。
普天間飛行場の移設先、同県名護市辺野古で抗議活動を続けている安次富浩(あしとみ・ひろし)さんは「試乗はセレモニーで、安定していたと言われても信用できない。安全性を証明したいなら、防衛相専用機にしたらいい」と皮肉った。
防衛相の試乗に対し、仲井真弘多知事も3日に「防衛相はテストパイロットでもないんだし、何か意味があるのか。よく分からない」と記者団に疑問を呈していた。』
食の安全性を問われれば試食してみせるのが政治家の仕事らしいから,飛行機の安全性が問われれば試乗してみせるというのもその延長線上の思考なのだろう。こういう水平思考しかできない政治家も十分危険だが,オスプレイの問題は水平飛行モードから垂直降下モードに切り替わる時の安定性だ.
砂漠の基地で運用するならまだしも,墜落率の高い飛行機をわざわざ住宅地の近くで運用しようというのだから,ヘリコプターに墜落された地元が猛反対するのも当然だろう.それをこんな意味の無いパフォーマンスをした挙げ句に「想像以上に飛行が安定していた」との感想を述べるのというのだからあきれたものだ.
まともにコメントするのもばからしいから「安全性を証明したいなら、防衛相専用機にしたらいい」と言った安次富浩(あしとみ・ひろし)さんに座布団一枚あげたいと思う.
インチキアセスメント?
2012年7月24日 社会の問題『ウミガメ、辺野古に頻繁に上陸 環境影響評価に疑問
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)を県内移設する予定地の名護市辺野古の海岸に、絶滅の恐れのあるウミガメが頻繁に上陸していることを沖縄防衛局で確認していたことが24日、分かった。防衛局は、昨年末に提出した環境影響評価(アセスメント)の評価書で「移設で消失する海浜はウミガメの上陸に適していない」として影響は限定的と結論付けていた。今回判明したのは反対の結果で、アセスの信頼性を揺るがし、移転問題に影響を与えそうだ。ウミガメのアセス対象期間は2007~08年だった。』
アセスメントも形式的なものだったってことだろうか.またしても国民の信頼を裏切るようなことをやってこのままで済むと思っているのだろうか.現代は情報の拡散が非常に早いから地域の問題として封じ込めようとしてもあっという間に世間に広まってしまうから隠し事などほとんど不可能だと思うのだが,やっている方は決してバレないとでも思っているのだろうか.
原発事故の安全性評価が最もいい例だが,自分たちの都合に合わせたいい加減な調査結果で審査を通したところで,ひとたび何かあればいいかげんな仕事ぶりは白日の元に晒され国民の広く知るところとなり,国への不信感と憎悪が拡大するから結局は自ら大きな障害つくりだす結果になるということがわからないのだろう.
この程度の情報管理能力も危機管理能力もない人達が国家的なプロジェクトを進めているというところが今のわが国の最大の問題点だろう.目的のために手段を選ばず強引に自分達の都合に合わせて国家事業をすすめるというやり方を改めない限り,今後は毎週金曜日の官邸前のデモのようなことが各地で頻発するようになるのではないだろうか.
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)を県内移設する予定地の名護市辺野古の海岸に、絶滅の恐れのあるウミガメが頻繁に上陸していることを沖縄防衛局で確認していたことが24日、分かった。防衛局は、昨年末に提出した環境影響評価(アセスメント)の評価書で「移設で消失する海浜はウミガメの上陸に適していない」として影響は限定的と結論付けていた。今回判明したのは反対の結果で、アセスの信頼性を揺るがし、移転問題に影響を与えそうだ。ウミガメのアセス対象期間は2007~08年だった。』
アセスメントも形式的なものだったってことだろうか.またしても国民の信頼を裏切るようなことをやってこのままで済むと思っているのだろうか.現代は情報の拡散が非常に早いから地域の問題として封じ込めようとしてもあっという間に世間に広まってしまうから隠し事などほとんど不可能だと思うのだが,やっている方は決してバレないとでも思っているのだろうか.
原発事故の安全性評価が最もいい例だが,自分たちの都合に合わせたいい加減な調査結果で審査を通したところで,ひとたび何かあればいいかげんな仕事ぶりは白日の元に晒され国民の広く知るところとなり,国への不信感と憎悪が拡大するから結局は自ら大きな障害つくりだす結果になるということがわからないのだろう.
この程度の情報管理能力も危機管理能力もない人達が国家的なプロジェクトを進めているというところが今のわが国の最大の問題点だろう.目的のために手段を選ばず強引に自分達の都合に合わせて国家事業をすすめるというやり方を改めない限り,今後は毎週金曜日の官邸前のデモのようなことが各地で頻発するようになるのではないだろうか.
『再稼働の大飯、断層調査へ 志賀原発も、専門家から要望続出
再稼働で注目される関西電力大飯原発(福井県)と、北陸電力志賀原発(石川県)の敷地内を走る断層の活動性を検討する経済産業省原子力安全・保安院の専門家会議が17日開かれ、委員から現地での再調査を求める意見が続出、再調査が避けられない状況となった。保安院は「意見は重く受け止める」としており、近く対応を決める。
大飯原発は3号機が今月1日に原子炉を起動、9日にフル稼働になった。4号機は18日に原子炉を起動する予定。
会議では、大飯原発内の破砕帯と呼ばれる軟弱な断層について「活断層の可能性を否定できる情報が出されていない」として、再調査を求める意見が相次いだ。』
『志賀原発下に活断層?「よく審査通ったと思う」
北陸電力志賀原発(石川県志賀町)直下の亀裂が活断層である可能性が高まった問題で、17日に経済産業省原子力安全・保安院が開いた専門家の意見聴取会では、北陸電の「原発の安全性を脅かすものではない」との説明に対し、専門家から「いいように解釈しすぎ」などと異論が相次いだ。
北陸電は、志賀原発の敷地地下に8本の亀裂(シーム)があり、1、2号機建屋の直下に2本の亀裂があるとしている。聴取会では、このうち1号機南西角の亀裂について、地層のずれは「波の浸食作用により形成された」と説明した。ところが、専門家からは異論が噴出。東北大大学院理学研究科の今泉俊文教授は「典型的な活断層だ。よく(建設許可の)審査が通ったと思う。北陸電の説明は全く理解できない」と憤った。北陸電の「専門家の判断だ」との説明にも、今泉教授は「そんな判断の仕方は初めて。いろんな人の目を通すべきだ」と一蹴した。
産業技術総合研究所活断層・地震研究センターの杉山雄一主幹研究員は「個人的には地震を起こすものではないように思える」としつつも、「ずれる可能性があり、それが建屋の下にあるなら、きちんと評価すべき」と現地調査を求めた。
京都大防災研究所の遠田晋次准教授は「北陸電は自分にいいように解釈しすぎで、腑ふに落ちない」と切って捨て、亀裂が形成された年代などの再評価を求めた。
今回は時間切れで2号機下の亀裂の説明ができなかったため、北陸電は次回に改めて説明する意向を示し、「説得力のある資料などを探し、丁寧な説明をしていきたい」として、現地での説明会も検討するという。』
『泊「軟弱な断層、考慮必要ない」 北電報告 保安院は再説明要請
北海道電力は17日、経済産業省原子力安全・保安院に対して、泊原発1~3号機(後志管内泊村)の敷地内を走る11本の破砕帯と呼ばれる軟弱な断層について「耐震設計上考慮する断層ではない」とする説明文書を提出した。専門家からは「データが不十分だ」などと異論が出て、保安院は北電に再説明を求めた。
活断層が原発に及ぼす影響を検討する専門家会議で示された。
泊原発の敷地内には、建設前のボーリング調査などで11本の破砕帯があると分かっている。
国の原発耐震指針では、13万~12万年前以降に動いた活断層の真上に原子炉など、重要施設を設置できないが、北電は破砕帯の新旧や地中状態を調べた結果、新しい時代のものではなく問題ないことを確認済みだと主張した。』
専門家というものは本来慎重であるべきもので,可能性のあることは追求するのでなければ存在価値がない.福島の事故以前のデーターは電力会社の都合にいいように解釈して原発の立地のお墨付きを与える原発ムラおかかえの専門家によるものだったのだろう.
すでに政治判断による安全性で再稼働している原発もあるが,国民の信頼を取り戻したいのなら全国的にもう一度本当の専門家によって審査し直すくらいのことはやって当然ではないだろうか.
再稼働で注目される関西電力大飯原発(福井県)と、北陸電力志賀原発(石川県)の敷地内を走る断層の活動性を検討する経済産業省原子力安全・保安院の専門家会議が17日開かれ、委員から現地での再調査を求める意見が続出、再調査が避けられない状況となった。保安院は「意見は重く受け止める」としており、近く対応を決める。
大飯原発は3号機が今月1日に原子炉を起動、9日にフル稼働になった。4号機は18日に原子炉を起動する予定。
会議では、大飯原発内の破砕帯と呼ばれる軟弱な断層について「活断層の可能性を否定できる情報が出されていない」として、再調査を求める意見が相次いだ。』
『志賀原発下に活断層?「よく審査通ったと思う」
北陸電力志賀原発(石川県志賀町)直下の亀裂が活断層である可能性が高まった問題で、17日に経済産業省原子力安全・保安院が開いた専門家の意見聴取会では、北陸電の「原発の安全性を脅かすものではない」との説明に対し、専門家から「いいように解釈しすぎ」などと異論が相次いだ。
北陸電は、志賀原発の敷地地下に8本の亀裂(シーム)があり、1、2号機建屋の直下に2本の亀裂があるとしている。聴取会では、このうち1号機南西角の亀裂について、地層のずれは「波の浸食作用により形成された」と説明した。ところが、専門家からは異論が噴出。東北大大学院理学研究科の今泉俊文教授は「典型的な活断層だ。よく(建設許可の)審査が通ったと思う。北陸電の説明は全く理解できない」と憤った。北陸電の「専門家の判断だ」との説明にも、今泉教授は「そんな判断の仕方は初めて。いろんな人の目を通すべきだ」と一蹴した。
産業技術総合研究所活断層・地震研究センターの杉山雄一主幹研究員は「個人的には地震を起こすものではないように思える」としつつも、「ずれる可能性があり、それが建屋の下にあるなら、きちんと評価すべき」と現地調査を求めた。
京都大防災研究所の遠田晋次准教授は「北陸電は自分にいいように解釈しすぎで、腑ふに落ちない」と切って捨て、亀裂が形成された年代などの再評価を求めた。
今回は時間切れで2号機下の亀裂の説明ができなかったため、北陸電は次回に改めて説明する意向を示し、「説得力のある資料などを探し、丁寧な説明をしていきたい」として、現地での説明会も検討するという。』
『泊「軟弱な断層、考慮必要ない」 北電報告 保安院は再説明要請
北海道電力は17日、経済産業省原子力安全・保安院に対して、泊原発1~3号機(後志管内泊村)の敷地内を走る11本の破砕帯と呼ばれる軟弱な断層について「耐震設計上考慮する断層ではない」とする説明文書を提出した。専門家からは「データが不十分だ」などと異論が出て、保安院は北電に再説明を求めた。
活断層が原発に及ぼす影響を検討する専門家会議で示された。
泊原発の敷地内には、建設前のボーリング調査などで11本の破砕帯があると分かっている。
国の原発耐震指針では、13万~12万年前以降に動いた活断層の真上に原子炉など、重要施設を設置できないが、北電は破砕帯の新旧や地中状態を調べた結果、新しい時代のものではなく問題ないことを確認済みだと主張した。』
専門家というものは本来慎重であるべきもので,可能性のあることは追求するのでなければ存在価値がない.福島の事故以前のデーターは電力会社の都合にいいように解釈して原発の立地のお墨付きを与える原発ムラおかかえの専門家によるものだったのだろう.
すでに政治判断による安全性で再稼働している原発もあるが,国民の信頼を取り戻したいのなら全国的にもう一度本当の専門家によって審査し直すくらいのことはやって当然ではないだろうか.
『仙台聴取会 騒然 発言者に東北電と原発推進団体幹部
政府は十五日、将来の原発比率について国民の意見を聴く二回目の意見聴取会を仙台市で開いた。抽選で選ばれた九人の発言者の中に、東北電力や原発推進団体の幹部二人が含まれ、「原発が不可欠」など従来通りの主張を展開し、会場から批判の声が上がった。
聴取会は、政府が提示した二〇三〇年時点の原発比率(1)0%(2)15%(3)20~25%の三案に対し、抽選で選ばれた各三人が意見を述べる形式。この日は進行側の手違いで、0%案四人、15%案二人、20~25%案三人だった。
このうち、原発の新増設を前提とする20~25%案に対し、東北電力の岡信慎一執行役員(企画部長)は「会社の考え方をまとめて話したい」と切り出し、電力の安定供給などを理由に、原発は必要と自社の主張を述べた。
また、原子力推進を目的に企業や商工団体などで組織する東北エネルギー懇談会の関口哲雄専務理事(元東北電力執行役員待遇)は「政府の案は再生可能エネルギーを大きく見積もりすぎだ」と、原発の積極的な活用を訴えた。
広く国民の意見を聴くはずの会が一転、原発推進団体の会と化し、参加者からは「被災者をばかにしているのか」など非難の声が上がった。司会者が「お静かに」を連発するが、会場の怒りは収まらず、一時中断した。
会場にいた仙台市の男性会社員(35)は「推進の考えでも、一般の人の意見を聞きたかった」と憤っていた。
事務局によると、聴取会には百七十五人の参加応募があり、抽選で百三十人を選んだ。うち意見表明を希望したのが九十三人で、0%案が六十六人、15%案が十四人、20~25%案が十三人。
これほど差があるのに、バランスを取ろうとするため、0%を支持した人はいずれも宮城県の人だったのに対し、15%と20~25%案は東北電力関係者二人のほか、東京都の会社員二人、神奈川県の会社員一人と、いびつな発言構成となった。
岡信、関口両氏は取材に対し、会社や組織からの依頼で応募したことを否定した。
政府代表として出席した細野豪志原発事故担当相は「抽選で選ぶので仕方ない。福島で開催するときは一般の県民の声が聞けるよう選び方を考えたい」と話した。』
『また電力社員が発言 名古屋聴取会
政府が発電量に占める将来の原発比率について国民の意見を直接聞く三回目の意見聴取会が十六日、名古屋市で開かれた。九人の発言者の中に中部電力の課長が含まれ、原発推進を主張した。会場の一部から「やらせだ」などと批判の声が上がり、一時騒然となった。
意見聴取会をめぐっては、十五日に開かれた仙台市の会場でも、東北電力や原発推進団体の幹部二人が発言者に選ばれており、公平性の確保や運営方法が問題視されそうだ。
発言したのは、中電原子力部に勤務する課長の岡本道明さん(46)。「個人的な意見として、原発をなくせば経済や消費が落ち込み、日本が衰退する」と述べ、原発の新増設を前提とする20~25%案に賛成の立場を表明。「35%案、45%案があれば選択していた」とも述べた。東京電力福島第一原発事故では「放射能の直接的な影響で亡くなった人は一人もいない」と言い切った。
岡本さんは聴取会後、報道陣に「会社には事前に個人として参加することを伝えた」と説明。事務局からも「個人なら聴取会の趣旨に反しない」と言われたという。
中電広報部の担当者は「会社の指示で出席や発言をさせたわけではない」と述べた。
0%案を支持する意見として「福島第一原発事故の原因がまだ究明されていない」「使用済み核燃料の処分法が確立されていない」があったほか、15%案の支持者は「国民生活への影響も考慮すべきだ」と訴えた。』
電力会社の社員は「放射能の直接的な影響で亡くなった人は一人もいない」なのかもしれないが,人災と認定された今回の事故の影響で亡くなった人はたくさんいることだろう.それなのにこの言い方では被災した人の神経を逆撫でするだけだ.この口で原発を推進すると言えば逆効果になることもわからないのだろうか.
そもそも原発によって直接的に利益を得る人たちの意見を聞く意味などあるのだろうか.「会社の考え方をまとめて話したい」などというのは論外だし,会社に所属して利害関係があるのに敢えて「個人として」と言える厚顔無恥さが電力会社の人たちの危機管理の本質と思えてしょうがない.こんなレベルの人たちには原発は危険すぎるおもちゃである.
抽選で選んだとは言っても,「意見表明を希望したのが九十三人で、0%案が六十六人、15%案が十四人、20~25%案が十三人。」だったら,各意見の人数は4:1:1くらいの比率が妥当だろうに,3人ずつとするのもおかしな話だ.これでは抽選した意味がない.細野豪志原発事故担当相は「抽選で選んだ」の意味がわかっているのだろうか.
公平性の確保や運営方法が問題視されても結局は同じようなことを繰り返して電力会社や原発ムラの人たちが「個人として」参加して電力会社の代弁をするようなものを意見聴取会と呼ぶのは「やらせ」どころか「イカサマ」ではないだろうか.
過去にも地元説明会に大挙して電力会社の社員が「サクラ」として潜り込むことがいつものことだったようだが,事故後もその体質はさっぱり変わっていないということだろう.
政府は十五日、将来の原発比率について国民の意見を聴く二回目の意見聴取会を仙台市で開いた。抽選で選ばれた九人の発言者の中に、東北電力や原発推進団体の幹部二人が含まれ、「原発が不可欠」など従来通りの主張を展開し、会場から批判の声が上がった。
聴取会は、政府が提示した二〇三〇年時点の原発比率(1)0%(2)15%(3)20~25%の三案に対し、抽選で選ばれた各三人が意見を述べる形式。この日は進行側の手違いで、0%案四人、15%案二人、20~25%案三人だった。
このうち、原発の新増設を前提とする20~25%案に対し、東北電力の岡信慎一執行役員(企画部長)は「会社の考え方をまとめて話したい」と切り出し、電力の安定供給などを理由に、原発は必要と自社の主張を述べた。
また、原子力推進を目的に企業や商工団体などで組織する東北エネルギー懇談会の関口哲雄専務理事(元東北電力執行役員待遇)は「政府の案は再生可能エネルギーを大きく見積もりすぎだ」と、原発の積極的な活用を訴えた。
広く国民の意見を聴くはずの会が一転、原発推進団体の会と化し、参加者からは「被災者をばかにしているのか」など非難の声が上がった。司会者が「お静かに」を連発するが、会場の怒りは収まらず、一時中断した。
会場にいた仙台市の男性会社員(35)は「推進の考えでも、一般の人の意見を聞きたかった」と憤っていた。
事務局によると、聴取会には百七十五人の参加応募があり、抽選で百三十人を選んだ。うち意見表明を希望したのが九十三人で、0%案が六十六人、15%案が十四人、20~25%案が十三人。
これほど差があるのに、バランスを取ろうとするため、0%を支持した人はいずれも宮城県の人だったのに対し、15%と20~25%案は東北電力関係者二人のほか、東京都の会社員二人、神奈川県の会社員一人と、いびつな発言構成となった。
岡信、関口両氏は取材に対し、会社や組織からの依頼で応募したことを否定した。
政府代表として出席した細野豪志原発事故担当相は「抽選で選ぶので仕方ない。福島で開催するときは一般の県民の声が聞けるよう選び方を考えたい」と話した。』
『また電力社員が発言 名古屋聴取会
政府が発電量に占める将来の原発比率について国民の意見を直接聞く三回目の意見聴取会が十六日、名古屋市で開かれた。九人の発言者の中に中部電力の課長が含まれ、原発推進を主張した。会場の一部から「やらせだ」などと批判の声が上がり、一時騒然となった。
意見聴取会をめぐっては、十五日に開かれた仙台市の会場でも、東北電力や原発推進団体の幹部二人が発言者に選ばれており、公平性の確保や運営方法が問題視されそうだ。
発言したのは、中電原子力部に勤務する課長の岡本道明さん(46)。「個人的な意見として、原発をなくせば経済や消費が落ち込み、日本が衰退する」と述べ、原発の新増設を前提とする20~25%案に賛成の立場を表明。「35%案、45%案があれば選択していた」とも述べた。東京電力福島第一原発事故では「放射能の直接的な影響で亡くなった人は一人もいない」と言い切った。
岡本さんは聴取会後、報道陣に「会社には事前に個人として参加することを伝えた」と説明。事務局からも「個人なら聴取会の趣旨に反しない」と言われたという。
中電広報部の担当者は「会社の指示で出席や発言をさせたわけではない」と述べた。
0%案を支持する意見として「福島第一原発事故の原因がまだ究明されていない」「使用済み核燃料の処分法が確立されていない」があったほか、15%案の支持者は「国民生活への影響も考慮すべきだ」と訴えた。』
電力会社の社員は「放射能の直接的な影響で亡くなった人は一人もいない」なのかもしれないが,人災と認定された今回の事故の影響で亡くなった人はたくさんいることだろう.それなのにこの言い方では被災した人の神経を逆撫でするだけだ.この口で原発を推進すると言えば逆効果になることもわからないのだろうか.
そもそも原発によって直接的に利益を得る人たちの意見を聞く意味などあるのだろうか.「会社の考え方をまとめて話したい」などというのは論外だし,会社に所属して利害関係があるのに敢えて「個人として」と言える厚顔無恥さが電力会社の人たちの危機管理の本質と思えてしょうがない.こんなレベルの人たちには原発は危険すぎるおもちゃである.
抽選で選んだとは言っても,「意見表明を希望したのが九十三人で、0%案が六十六人、15%案が十四人、20~25%案が十三人。」だったら,各意見の人数は4:1:1くらいの比率が妥当だろうに,3人ずつとするのもおかしな話だ.これでは抽選した意味がない.細野豪志原発事故担当相は「抽選で選んだ」の意味がわかっているのだろうか.
公平性の確保や運営方法が問題視されても結局は同じようなことを繰り返して電力会社や原発ムラの人たちが「個人として」参加して電力会社の代弁をするようなものを意見聴取会と呼ぶのは「やらせ」どころか「イカサマ」ではないだろうか.
過去にも地元説明会に大挙して電力会社の社員が「サクラ」として潜り込むことがいつものことだったようだが,事故後もその体質はさっぱり変わっていないということだろう.
『実はエスカレーターでは「歩いてはいけない」 事故続発で「立ち止まり」呼びかける動きも
エスカレーターは歩いて上り下りするのが一般的になっているが、実はこれは危険な利用方法なのだ。そもそも安全規定も歩くことを前提にしていない。各地で「歩行禁止」を呼びかける動きが広まってきているが、歩行する人はなかなか減らないのが実態だ。
事故が続出している神奈川県川崎市は、JR川崎駅で利用マナーを向上させるキャンペーンを行っている。
川崎市では今年に入ってすでに8件の事故
川崎市は2012年7月2日から6日まで、JR川崎駅東西自由通路エスカレーターの上り口・下り口付近で、チラシ配布やプラカード掲出などで「エスカレーターは歩かず、立ち止まって利用する」ことを呼びかけた。
同市ではエスカレーターの事故が頻発している。11年12月には溝口駅で女性が手すりに左手を挟まれ中指と薬指を切断する大けがを負ったほか、07年8月には川崎駅で破損していた部分に左足を挟まれ親指を切断、08年11月には川崎駅で数人がはがれた金具にブーツやジーンズを引っ掛けるという事故があった。
市消防局によると、市内では12年1月1日から7月3日までですでに8件のエスカレーター事故が起こっているという。高齢者がエスカレーターに乗る際、または乗っている最中に転倒して怪我をするケースが多いそうだ。
エスカレーター歩行は「目的外使用」
一般社団法人 日本エレベーター協会によると、エスカレーター歩行はエスカレーターの普及にともなって自然発生的に増えていったという。2008年1月から09年12月までの2年間の転倒事故件数は約1200件で、5年前は約670件、その5年前は約420件、そのまた5年前は約320件と年々急増している。すべての転倒事故が歩行に起因するものかどうかは確認していないが、歩行による転倒事故は少なくないとしている。
エスカレーターの安全規定は歩くことを前提にしておらず、エスカレーターを歩行することは「目的外使用」にあたるそうだ。名古屋市営地下鉄、大阪市営地下鉄など、歩行を禁止している地方の交通局もある。しかし抑止にはつながっていないのが現状だという。
関東ではエスカレーターの右側を歩行者のために空け、関西ではその逆、というのが一般化しているが、体が不自由で、やむをえず歩行者側に立ち止まる利用者もいる。中にはそうした人を後ろから罵倒するケースも見かけるという。また、エスカレーターはまれに急停止する場合があり、歩行していると転倒する可能性が高い。金属製なので、軽いけがでは済まない場合もある。自分だけでなく周りの人を巻き込むこともあり、エスカレーター歩行はやめてほしい、と話している。』
以前にも歩いて上がってきた人とぶつかった人が転倒して将棋倒しになる大きな事故があってニュースになっていたが,そもそもエスカレーターの上を歩いてはいけないということを知っている人は一体どれ位いるのだろうか.
駅などでみんなが右側を開けて乗っているのを見ると自分もついならってそまうのだが,そうすると当然のごとく歩いて上がってくるひとがいるわけで,ある意味で事故発生の要因を作るだしているような気がするし,歩いてはいけないのだったら2列に並んだ方が待ち時間が少なくなり混雑も減るとも思われる.
わざわざ右側を空けた上に旅行用のスーツケースを腕や手にぶつけられて頭にきたことも2度や3度ではないという人も私だけではないだろう.そう考えるともっと歩行禁止を周知徹底させるか,1列しかないエスカレーターに替えるかするしかないのではないだろうか.
日本は民度が高いから個人の良識にまかせるという意見もあるかもしれないが,今やそんな日本人ばかりではないから,本当に事故を減らしたいならエスカレーターを交換するしかないだろう.今や日本人にも民度を期待できない人はたくさんいるし,そのような人にルールを説明したところで逆切れされるのがオチだろう.
優先席に座っている人に注意することも,エスカレーターの上を歩いて上る人を注意するのも無駄なことだ.やってはイケナイ事を敢えてやるような人に何を言っても無駄なことだろう.これからはやってはイケナイ事は出来ないようにしてリスクを減らしたり,やってはイケナイ事を敢えてやるような人に対しては社会的な制裁をより厳しくするべきだろう.
エスカレーターは歩いて上り下りするのが一般的になっているが、実はこれは危険な利用方法なのだ。そもそも安全規定も歩くことを前提にしていない。各地で「歩行禁止」を呼びかける動きが広まってきているが、歩行する人はなかなか減らないのが実態だ。
事故が続出している神奈川県川崎市は、JR川崎駅で利用マナーを向上させるキャンペーンを行っている。
川崎市では今年に入ってすでに8件の事故
川崎市は2012年7月2日から6日まで、JR川崎駅東西自由通路エスカレーターの上り口・下り口付近で、チラシ配布やプラカード掲出などで「エスカレーターは歩かず、立ち止まって利用する」ことを呼びかけた。
同市ではエスカレーターの事故が頻発している。11年12月には溝口駅で女性が手すりに左手を挟まれ中指と薬指を切断する大けがを負ったほか、07年8月には川崎駅で破損していた部分に左足を挟まれ親指を切断、08年11月には川崎駅で数人がはがれた金具にブーツやジーンズを引っ掛けるという事故があった。
市消防局によると、市内では12年1月1日から7月3日までですでに8件のエスカレーター事故が起こっているという。高齢者がエスカレーターに乗る際、または乗っている最中に転倒して怪我をするケースが多いそうだ。
エスカレーター歩行は「目的外使用」
一般社団法人 日本エレベーター協会によると、エスカレーター歩行はエスカレーターの普及にともなって自然発生的に増えていったという。2008年1月から09年12月までの2年間の転倒事故件数は約1200件で、5年前は約670件、その5年前は約420件、そのまた5年前は約320件と年々急増している。すべての転倒事故が歩行に起因するものかどうかは確認していないが、歩行による転倒事故は少なくないとしている。
エスカレーターの安全規定は歩くことを前提にしておらず、エスカレーターを歩行することは「目的外使用」にあたるそうだ。名古屋市営地下鉄、大阪市営地下鉄など、歩行を禁止している地方の交通局もある。しかし抑止にはつながっていないのが現状だという。
関東ではエスカレーターの右側を歩行者のために空け、関西ではその逆、というのが一般化しているが、体が不自由で、やむをえず歩行者側に立ち止まる利用者もいる。中にはそうした人を後ろから罵倒するケースも見かけるという。また、エスカレーターはまれに急停止する場合があり、歩行していると転倒する可能性が高い。金属製なので、軽いけがでは済まない場合もある。自分だけでなく周りの人を巻き込むこともあり、エスカレーター歩行はやめてほしい、と話している。』
以前にも歩いて上がってきた人とぶつかった人が転倒して将棋倒しになる大きな事故があってニュースになっていたが,そもそもエスカレーターの上を歩いてはいけないということを知っている人は一体どれ位いるのだろうか.
駅などでみんなが右側を開けて乗っているのを見ると自分もついならってそまうのだが,そうすると当然のごとく歩いて上がってくるひとがいるわけで,ある意味で事故発生の要因を作るだしているような気がするし,歩いてはいけないのだったら2列に並んだ方が待ち時間が少なくなり混雑も減るとも思われる.
わざわざ右側を空けた上に旅行用のスーツケースを腕や手にぶつけられて頭にきたことも2度や3度ではないという人も私だけではないだろう.そう考えるともっと歩行禁止を周知徹底させるか,1列しかないエスカレーターに替えるかするしかないのではないだろうか.
日本は民度が高いから個人の良識にまかせるという意見もあるかもしれないが,今やそんな日本人ばかりではないから,本当に事故を減らしたいならエスカレーターを交換するしかないだろう.今や日本人にも民度を期待できない人はたくさんいるし,そのような人にルールを説明したところで逆切れされるのがオチだろう.
優先席に座っている人に注意することも,エスカレーターの上を歩いて上る人を注意するのも無駄なことだ.やってはイケナイ事を敢えてやるような人に何を言っても無駄なことだろう.これからはやってはイケナイ事は出来ないようにしてリスクを減らしたり,やってはイケナイ事を敢えてやるような人に対しては社会的な制裁をより厳しくするべきだろう.
『大津・中2自殺:9カ月後、異例の学校捜索
大津市で昨年10月、いじめを受けていた同市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺した問題は11日、滋賀県警が中学校や市役所の強制捜査に着手する極めて異例の事態に発展した。男子生徒が自宅マンションから飛び降りてから既に9カ月。いじめの実態にどこまで迫れるのか。捜査員は険しい表情で校長室、職員室などに入り、約5時間に及んだ捜索は日付をまたいだ。
県警は11日、昨年9月の男子生徒に対する同級生3人の暴行容疑で家宅捜索の令状を取った。自殺した男子生徒が通っていた大津市立中学では午後7時半ごろ、県警捜査員が乗った車3台が正門から家宅捜索に入った。明かりがついた部屋は、中の様子が見えないようカーテンが閉められたまま。家宅捜索をニュース速報で知った中学生や保護者が正門に集まったが、学校の教員ら数人が出てきて帰宅を促していた。
長男が自殺した男子生徒と同級生だったという保護者の男性会社員(47)は「隠されていたことが多くおかしい。少なくとも担任ら学校の一部は知っていたはずで、大人が行動しなければいけないのに行動しなかった。学校や市教委には不信感がある。警察の捜索も遅いが、真実が分かることを期待している」と話した。
同市役所では、市教委事務局がある市役所別館(同市御陵町)2階に向かった捜査員らがまず、教育長室へ。今回のいじめ問題の調査を担当する学校教育課などのエリアで捜索を始めた。』
ネットを中心に社会的な反響があまりにも大きかったので本格的な捜査をする気にでもなったのだろうか.捜査は暴行や傷害の有無を中心に調べるようであるが,それならば本当に自殺という事でいいのかどうかももう一度よく検証して見る必要があるような気もする.
過去のストーカー殺人事件の時にもあったことであるが,男女間や学生同士の問題の場合に警察の初動捜査が甘いような気がするのだが何故なのだろうか.まさか女,子供だからという訳ではないだろうが,いつも初期の対応のまずさから救えた命を失っているように思うのは私だけだろうか.
もっとも警察の責任をどうこう言うつもりはないし,担任の教師やいじめた側の親の責任が重大であることは言うまでもないだろう.
大津市で昨年10月、いじめを受けていた同市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺した問題は11日、滋賀県警が中学校や市役所の強制捜査に着手する極めて異例の事態に発展した。男子生徒が自宅マンションから飛び降りてから既に9カ月。いじめの実態にどこまで迫れるのか。捜査員は険しい表情で校長室、職員室などに入り、約5時間に及んだ捜索は日付をまたいだ。
県警は11日、昨年9月の男子生徒に対する同級生3人の暴行容疑で家宅捜索の令状を取った。自殺した男子生徒が通っていた大津市立中学では午後7時半ごろ、県警捜査員が乗った車3台が正門から家宅捜索に入った。明かりがついた部屋は、中の様子が見えないようカーテンが閉められたまま。家宅捜索をニュース速報で知った中学生や保護者が正門に集まったが、学校の教員ら数人が出てきて帰宅を促していた。
長男が自殺した男子生徒と同級生だったという保護者の男性会社員(47)は「隠されていたことが多くおかしい。少なくとも担任ら学校の一部は知っていたはずで、大人が行動しなければいけないのに行動しなかった。学校や市教委には不信感がある。警察の捜索も遅いが、真実が分かることを期待している」と話した。
同市役所では、市教委事務局がある市役所別館(同市御陵町)2階に向かった捜査員らがまず、教育長室へ。今回のいじめ問題の調査を担当する学校教育課などのエリアで捜索を始めた。』
ネットを中心に社会的な反響があまりにも大きかったので本格的な捜査をする気にでもなったのだろうか.捜査は暴行や傷害の有無を中心に調べるようであるが,それならば本当に自殺という事でいいのかどうかももう一度よく検証して見る必要があるような気もする.
過去のストーカー殺人事件の時にもあったことであるが,男女間や学生同士の問題の場合に警察の初動捜査が甘いような気がするのだが何故なのだろうか.まさか女,子供だからという訳ではないだろうが,いつも初期の対応のまずさから救えた命を失っているように思うのは私だけだろうか.
もっとも警察の責任をどうこう言うつもりはないし,担任の教師やいじめた側の親の責任が重大であることは言うまでもないだろう.
『中2「自殺練習」アンケ非公表、隠蔽批判に市は
大津市で昨年10月、市立中2年の男子生徒(当時13歳)が自宅マンションから飛び降り自殺したとされる問題を巡り、市教委が4日に開いた記者会見で、市教委は複数の生徒が全校アンケートに「自殺の練習をさせられていた」とした回答を非公表としたことについて、「公表する内容について、かなり慎重に確認しており、隠したとは考えていない」と強調した。
市教委は男子生徒の死亡直後の昨年10月中旬、全校生徒を対象にアンケートを行い、自分で見聞きした内容が記名で書かれた回答だけを基に、〈いじめ〉を公表。「自殺を練習させられた」「金を脅し取られた」などは無記名か伝聞のいずれかだったことから、「事実確認できない」として公表を見送ったという。
沢村憲次・市教育長はこの日の記者会見で、この問題について説明。記名で回答した生徒に聞き取り調査を行い、「自殺を練習させられた」との情報については発信者までたどり着いたものの、確信が持てなかった、とした。
市教委がアンケート結果について、一部を非公表としていたとの報道を受け、市教委には4日夜までに電話やメール計約300件が寄せられたという。大半は「なぜ、公表しなかったのか」「どうなっている」などの批判だった。』
『いじめた側にも人権…「自殺練習」真偽確認せず
大津市の市立中学2年男子生徒が自殺したことを巡って行われた全校アンケートで「(男子生徒が)自殺の練習をさせられていた」との回答を市教委が公表しなかった問題で、市教委が加害者とされる同級生らに対して直接、真偽を確認していなかったことがわかった。
市教委はこれまで、非公表にした理由を「事実を確認できなかったため」と説明していた。
市教委によると、「自殺の練習」は、生徒16人が回答に記していた。うち実名で回答した4人には聞き取りをしたが、事実は確認できず、それ以上の調査もしなかったという。加害者とされる同級生らにも聞き取りを行う機会はあったが、「練習」については一切尋ねなかったとしている。
その理由について、市教委は読売新聞に対し、「事実確認は可能な範囲でしたつもりだが、いじめた側にも人権があり、教育的配慮が必要と考えた。『自殺の練習』を問いただせば、当事者の生徒や保護者に『いじめを疑っているのか』と不信感を抱かれるかもしれない、との判断もあった」と説明。結局、事実がつかめなかったとして、非公表にしたという。』
「死人に口無し」と言うが,「いじめた側にも人権があり、教育的配慮が必要」というなら生きている加害者の人権保護や教育的配慮の方が自殺した生徒や今いじめられている生徒の人権より重要だと言っているのと同じだろう.
おまけにわざわざ全校アンケートをとったのにその内容やそれに対する事実確認の結果を非公表にしてしまったのでは何のためのアンケートだったかもわからない.これでは一応はいじめがあったかどうか調査はしましたよという体裁を整えただけだと思われてもしょうがないだろう.
加害者とされる生徒の母親の反論などもネットに流れていたが,市教委がこんな程度ではこれからもいじめはなくなることはないだろう.自殺した生徒は可哀想だとは思うし,無記名でアンケートに答えた生徒達の気持ちもわからないでもないが,これでは自殺しても社会的には無意味だったということだ.
本当に死ぬ程の勇気があるのならば,せめていじめた生徒の名前をネットに晒して問題がまわりからよく見えるようにするとかして,いじめた生徒に反撃して戦う姿勢を見せないと事なかれ主義の市教委などは真剣に対応しないんじゃないだろうか.
追記:
『中2自殺、外部有識者の調査委設置へ 越大津市長
大津市立中学の男子生徒(当時13)の自殺をめぐり、同市の越直美市長は6日の定例会見で「外部の有識者を交えた調査委員会を立ち上げる」と、事実関係を改めて調査する意向を示した。「訴訟では、(市は)いじめと自殺との因果関係が認められないとしているが、調査委員会の調査結果によっては、見直す可能性もある」と話した。
越市長は会見冒頭、「中学生が自らの命を絶ったことに改めて哀悼の意を表したい」と涙ながらに述べた。これまでの調査については「もっとできるところがあるのでは、と思う」と指摘した。』
人が死んでいるのだから調査委員会の設置は妥当だろう.児童虐待もそうだが声を出せないまま死んで行く子供達のために全国的に行政側のもっと積極的な対応が必要だろう.
大津市で昨年10月、市立中2年の男子生徒(当時13歳)が自宅マンションから飛び降り自殺したとされる問題を巡り、市教委が4日に開いた記者会見で、市教委は複数の生徒が全校アンケートに「自殺の練習をさせられていた」とした回答を非公表としたことについて、「公表する内容について、かなり慎重に確認しており、隠したとは考えていない」と強調した。
市教委は男子生徒の死亡直後の昨年10月中旬、全校生徒を対象にアンケートを行い、自分で見聞きした内容が記名で書かれた回答だけを基に、〈いじめ〉を公表。「自殺を練習させられた」「金を脅し取られた」などは無記名か伝聞のいずれかだったことから、「事実確認できない」として公表を見送ったという。
沢村憲次・市教育長はこの日の記者会見で、この問題について説明。記名で回答した生徒に聞き取り調査を行い、「自殺を練習させられた」との情報については発信者までたどり着いたものの、確信が持てなかった、とした。
市教委がアンケート結果について、一部を非公表としていたとの報道を受け、市教委には4日夜までに電話やメール計約300件が寄せられたという。大半は「なぜ、公表しなかったのか」「どうなっている」などの批判だった。』
『いじめた側にも人権…「自殺練習」真偽確認せず
大津市の市立中学2年男子生徒が自殺したことを巡って行われた全校アンケートで「(男子生徒が)自殺の練習をさせられていた」との回答を市教委が公表しなかった問題で、市教委が加害者とされる同級生らに対して直接、真偽を確認していなかったことがわかった。
市教委はこれまで、非公表にした理由を「事実を確認できなかったため」と説明していた。
市教委によると、「自殺の練習」は、生徒16人が回答に記していた。うち実名で回答した4人には聞き取りをしたが、事実は確認できず、それ以上の調査もしなかったという。加害者とされる同級生らにも聞き取りを行う機会はあったが、「練習」については一切尋ねなかったとしている。
その理由について、市教委は読売新聞に対し、「事実確認は可能な範囲でしたつもりだが、いじめた側にも人権があり、教育的配慮が必要と考えた。『自殺の練習』を問いただせば、当事者の生徒や保護者に『いじめを疑っているのか』と不信感を抱かれるかもしれない、との判断もあった」と説明。結局、事実がつかめなかったとして、非公表にしたという。』
「死人に口無し」と言うが,「いじめた側にも人権があり、教育的配慮が必要」というなら生きている加害者の人権保護や教育的配慮の方が自殺した生徒や今いじめられている生徒の人権より重要だと言っているのと同じだろう.
おまけにわざわざ全校アンケートをとったのにその内容やそれに対する事実確認の結果を非公表にしてしまったのでは何のためのアンケートだったかもわからない.これでは一応はいじめがあったかどうか調査はしましたよという体裁を整えただけだと思われてもしょうがないだろう.
加害者とされる生徒の母親の反論などもネットに流れていたが,市教委がこんな程度ではこれからもいじめはなくなることはないだろう.自殺した生徒は可哀想だとは思うし,無記名でアンケートに答えた生徒達の気持ちもわからないでもないが,これでは自殺しても社会的には無意味だったということだ.
本当に死ぬ程の勇気があるのならば,せめていじめた生徒の名前をネットに晒して問題がまわりからよく見えるようにするとかして,いじめた生徒に反撃して戦う姿勢を見せないと事なかれ主義の市教委などは真剣に対応しないんじゃないだろうか.
追記:
『中2自殺、外部有識者の調査委設置へ 越大津市長
大津市立中学の男子生徒(当時13)の自殺をめぐり、同市の越直美市長は6日の定例会見で「外部の有識者を交えた調査委員会を立ち上げる」と、事実関係を改めて調査する意向を示した。「訴訟では、(市は)いじめと自殺との因果関係が認められないとしているが、調査委員会の調査結果によっては、見直す可能性もある」と話した。
越市長は会見冒頭、「中学生が自らの命を絶ったことに改めて哀悼の意を表したい」と涙ながらに述べた。これまでの調査については「もっとできるところがあるのでは、と思う」と指摘した。』
人が死んでいるのだから調査委員会の設置は妥当だろう.児童虐待もそうだが声を出せないまま死んで行く子供達のために全国的に行政側のもっと積極的な対応が必要だろう.
『東電社内事故調が報告書 「原因は想定外の津波」
東京電力の福島第1原発事故調査委員会(社内事故調)は20日、事故対応の状況や放射性物質の飛散状況の分析結果などを盛り込んだ最終報告書を公表。事故原因については「想定した高さを上回る津波の発生」とし、従来の主張を繰り返した。
調査には外部の専門家による検証委員会も設けられていたが、東電は「調査過程で意見を聞いた」として、報告書には検証内容を具体的に盛り込まず、調査の客観性、妥当性に疑問を残した。』
過去に同様の津波があった記録が実際には存在していたのに,きちんとした調査も行わず非科学的な想定をしたことが真の事故原因であることは明らかなのに,わざわざこんな報告書を作ってなんの意味があるのだろうか.
おまけに外部の専門家の検証過程や検証内容が明らかでないのなら,今までと同じ自分たちに都合のいい作文にすぎないだろう.もっとも自分から非を認めたら今後の裁判では負け続けることが確定するだろうから他に言いようがないのかもしれない.
もっとも高さは想定外でも津波の発生は想定していたのだろうから,検証すべきはなぜ津波の高さの想定を間違えたのかという点で,その高さを決めるまでの経過をもっと詳細に検証して原子力ムラの中に存在する問題点を洗い出す必要があるだろう.
そういう自らの問題点を真摯に反省する姿勢を見せてくれないかぎり,電力会社など二度と信用する気がしないのは私だけではないだろう.
東京電力の福島第1原発事故調査委員会(社内事故調)は20日、事故対応の状況や放射性物質の飛散状況の分析結果などを盛り込んだ最終報告書を公表。事故原因については「想定した高さを上回る津波の発生」とし、従来の主張を繰り返した。
調査には外部の専門家による検証委員会も設けられていたが、東電は「調査過程で意見を聞いた」として、報告書には検証内容を具体的に盛り込まず、調査の客観性、妥当性に疑問を残した。』
過去に同様の津波があった記録が実際には存在していたのに,きちんとした調査も行わず非科学的な想定をしたことが真の事故原因であることは明らかなのに,わざわざこんな報告書を作ってなんの意味があるのだろうか.
おまけに外部の専門家の検証過程や検証内容が明らかでないのなら,今までと同じ自分たちに都合のいい作文にすぎないだろう.もっとも自分から非を認めたら今後の裁判では負け続けることが確定するだろうから他に言いようがないのかもしれない.
もっとも高さは想定外でも津波の発生は想定していたのだろうから,検証すべきはなぜ津波の高さの想定を間違えたのかという点で,その高さを決めるまでの経過をもっと詳細に検証して原子力ムラの中に存在する問題点を洗い出す必要があるだろう.
そういう自らの問題点を真摯に反省する姿勢を見せてくれないかぎり,電力会社など二度と信用する気がしないのは私だけではないだろう.
もんじゅは終了しました.
2012年6月19日 社会の問題 コメント (2)
『<核燃サイクル秘密会議>「もんじゅに不利」シナリオ隠蔽
内閣府原子力委員会が原発推進側だけを集めて開いた「勉強会」と称する秘密会議で3月8日、使用済み核燃料を再利用する核燃サイクル政策の見直しを検討していた原子力委の小委員会に提出予定の四つのモデルケース(シナリオ)について議論し、このうち高速増殖炉(FBR)推進に不利なシナリオを隠すことを決めていたことが分かった。「表」の小委員会の会議には三つのシナリオしか提出されておらず、秘密会議が核心部分に影響を与えていた実態が一層鮮明になった。
【核燃サイクル秘密会議】書き換え・隠蔽、ゆがむ政策
小委員会は三つのシナリオを含む取りまとめを終えている。今後、政府の「エネルギー・環境会議」に提出される予定で、対応が注目される。
核燃サイクルは使用済み核燃料を再処理し燃料として再利用する。再利用の際、高速中性子で核分裂を起こす原子炉を総称して高速炉(FR)といい、このうち元の燃料よりも多くの燃料を生み出す「もんじゅ」のような炉をFBRと呼ぶ。
シナリオ1は全使用済み核燃料を再処理し(全量再処理)FR実用化を目指す。シナリオ2は一部を再処理し残りを貯蔵しつつFR実用化を判断するための研究開発を行う(実用化留保)。シナリオ3は一部を再処理し残りを捨て(直接処分)FR実用化を中止。シナリオ4は再処理せずすべて捨て(全量直接処分)FR実用化は中止する=チャート図。シナリオ1、2ならば、もんじゅ関連の研究開発を続行できるが、3と4は中止を意味する。
3月8日の秘密会議に四つのシナリオが提示されると、参加者は「小委員会の議論は全量再処理のシナリオ1や全量直接処分の4ではなく必ず真ん中(2か3)に寄ってくる。シナリオ3があると、これを選ぶ人(小委員会のメンバー)が出てくる」と発言。別の参加者が「ここは勝負どころ。シナリオ2が望ましく3はなくすべきだ」と述べ、シナリオ3を外すことを決めた。3月22日の秘密会議にも四つのシナリオが記載された文書が配布されたが、司会役が「四つにしようという話があったが三つにした」と結論だけ伝え、議論はしなかった。
3月8日の秘密会議に職員5人が出席した内閣府原子力政策担当室は取材に「記者の質問がブラフ(はったり)かもしれず回答できない」としている。
◇ことば=高速炉(FR)と高速増殖炉(FBR)
現在主流の軽水炉は水で減速した熱中性子で核分裂反応を起こす。これに対し、高速の中性子で核分裂反応を起こすのが高速炉。軽水炉で利用できないウラン238を核分裂可能なプルトニウム239に変えて燃料として利用できるため、ウラン資源節約に役立つ。FRのうち消費量より多くのプルトニウム239を生み出す(増殖)のがFBR。国内では「もんじゅ」が95年12月にナトリウム漏れ事故を起こすなどのトラブルで試験運転が再開できていない。英独など海外では撤退が相次いでいる。』
またも隠蔽の話でいつもながら厭になる.自分たちに都合のいい話を進めるために情報を隠蔽し議論の場を作らず国民に疑問を抱かせないように誘導するというのがわが国の官僚達のやり方だということがわかる.
日本人は議論が下手だとよく言われるし,両極端の意見は嫌われ中庸を選ぶ傾向にあるから,ちょうどトランプのばば抜きのように残り3枚から真ん中のカードを引かせるようにするために1枚はわざと隠したつもりなのだろうか.
しかし,そんなことをしても現実にはカードは4枚あるのだからゲームが終わる頃には隠した1枚のためにカードの数が合わなくなってインチキがバレるとは思わなかったのだろうか.
今の日本の原子力行政はまだゲームの途中だったのだが,地震と津波という想定外の自然現象のために何枚も隠していたカードが次々と国民の見えるところに出て来てしまった状態のように思う.なんだか滑稽な感じさえするが,重ねてきたインチキがバレたくせに開き直っているように見える原子力ムラの人たちの厚顔無恥には呆れ果てたものだ.
再稼働が決まった大飯原発も直下の断層の再評価,フィルター付きベントの設置,防潮堤のかさ上げ,免震事務棟の建設などは事故を起こした福島とあまり変わらない状況なのに「福島のような事故は起きない」と言う根拠は何なのだろうか.
結局,彼らの頭にあるのは産業界からの圧力に対する自分たちの都合と,近いうちにはもう二度とあんな大地震は来ないだろうという思い込みだけで,原発周辺地域の人たちの生命や安全などはいざとなったらしょうがないと諦めるつもりでいるとしか思えないのだ.
内閣府原子力委員会が原発推進側だけを集めて開いた「勉強会」と称する秘密会議で3月8日、使用済み核燃料を再利用する核燃サイクル政策の見直しを検討していた原子力委の小委員会に提出予定の四つのモデルケース(シナリオ)について議論し、このうち高速増殖炉(FBR)推進に不利なシナリオを隠すことを決めていたことが分かった。「表」の小委員会の会議には三つのシナリオしか提出されておらず、秘密会議が核心部分に影響を与えていた実態が一層鮮明になった。
【核燃サイクル秘密会議】書き換え・隠蔽、ゆがむ政策
小委員会は三つのシナリオを含む取りまとめを終えている。今後、政府の「エネルギー・環境会議」に提出される予定で、対応が注目される。
核燃サイクルは使用済み核燃料を再処理し燃料として再利用する。再利用の際、高速中性子で核分裂を起こす原子炉を総称して高速炉(FR)といい、このうち元の燃料よりも多くの燃料を生み出す「もんじゅ」のような炉をFBRと呼ぶ。
シナリオ1は全使用済み核燃料を再処理し(全量再処理)FR実用化を目指す。シナリオ2は一部を再処理し残りを貯蔵しつつFR実用化を判断するための研究開発を行う(実用化留保)。シナリオ3は一部を再処理し残りを捨て(直接処分)FR実用化を中止。シナリオ4は再処理せずすべて捨て(全量直接処分)FR実用化は中止する=チャート図。シナリオ1、2ならば、もんじゅ関連の研究開発を続行できるが、3と4は中止を意味する。
3月8日の秘密会議に四つのシナリオが提示されると、参加者は「小委員会の議論は全量再処理のシナリオ1や全量直接処分の4ではなく必ず真ん中(2か3)に寄ってくる。シナリオ3があると、これを選ぶ人(小委員会のメンバー)が出てくる」と発言。別の参加者が「ここは勝負どころ。シナリオ2が望ましく3はなくすべきだ」と述べ、シナリオ3を外すことを決めた。3月22日の秘密会議にも四つのシナリオが記載された文書が配布されたが、司会役が「四つにしようという話があったが三つにした」と結論だけ伝え、議論はしなかった。
3月8日の秘密会議に職員5人が出席した内閣府原子力政策担当室は取材に「記者の質問がブラフ(はったり)かもしれず回答できない」としている。
◇ことば=高速炉(FR)と高速増殖炉(FBR)
現在主流の軽水炉は水で減速した熱中性子で核分裂反応を起こす。これに対し、高速の中性子で核分裂反応を起こすのが高速炉。軽水炉で利用できないウラン238を核分裂可能なプルトニウム239に変えて燃料として利用できるため、ウラン資源節約に役立つ。FRのうち消費量より多くのプルトニウム239を生み出す(増殖)のがFBR。国内では「もんじゅ」が95年12月にナトリウム漏れ事故を起こすなどのトラブルで試験運転が再開できていない。英独など海外では撤退が相次いでいる。』
またも隠蔽の話でいつもながら厭になる.自分たちに都合のいい話を進めるために情報を隠蔽し議論の場を作らず国民に疑問を抱かせないように誘導するというのがわが国の官僚達のやり方だということがわかる.
日本人は議論が下手だとよく言われるし,両極端の意見は嫌われ中庸を選ぶ傾向にあるから,ちょうどトランプのばば抜きのように残り3枚から真ん中のカードを引かせるようにするために1枚はわざと隠したつもりなのだろうか.
しかし,そんなことをしても現実にはカードは4枚あるのだからゲームが終わる頃には隠した1枚のためにカードの数が合わなくなってインチキがバレるとは思わなかったのだろうか.
今の日本の原子力行政はまだゲームの途中だったのだが,地震と津波という想定外の自然現象のために何枚も隠していたカードが次々と国民の見えるところに出て来てしまった状態のように思う.なんだか滑稽な感じさえするが,重ねてきたインチキがバレたくせに開き直っているように見える原子力ムラの人たちの厚顔無恥には呆れ果てたものだ.
再稼働が決まった大飯原発も直下の断層の再評価,フィルター付きベントの設置,防潮堤のかさ上げ,免震事務棟の建設などは事故を起こした福島とあまり変わらない状況なのに「福島のような事故は起きない」と言う根拠は何なのだろうか.
結局,彼らの頭にあるのは産業界からの圧力に対する自分たちの都合と,近いうちにはもう二度とあんな大地震は来ないだろうという思い込みだけで,原発周辺地域の人たちの生命や安全などはいざとなったらしょうがないと諦めるつもりでいるとしか思えないのだ.
『一体改革で3党修正協議 「消費増税ありき」の歩み寄り
社会保障・税一体改革関連法案をめぐる15日の民主、自民、公明3党の税制分野の修正協議で、消費税増税へ向けた手続きは大詰めを迎えた。しかし、低所得者対策や自動車・住宅取得時の負担軽減策など3党間で隔たりのあるテーマについては、法案の採決を優先し、軒並み棚上げされる公算が大きい。増税ありきで結論を急ぐ姿勢に納税者からの批判も予想される。
増税時の低所得者の負担緩和策では、3党は2014年4月に消費税率を8%に引き上げた時点で、一定以下の年収の人に現金を配る「簡素な給付措置」を実施することで合意した。給付対象や金額など詳細は法案成立後に検討する方針だ。
具体論で、自民党は消費税率を5%にした1997年に低所得者らに1万円を1回限りで支給した措置を参考にするよう求めたが、公明党が「手続きは簡素でも内容はしっかりしたものであるべきだ」(幹部)と手厚い給付を要求した。民主党も複数年にわたって支給したい考えだが、バラマキになれば増税による税収増の効果が薄れる懸念もある。
税率が10%になってからの対策は、民主党が個人の所得などを一元管理する共通番号制度の本格稼働を前提に、納税額の一部を戻す「給付付き税額控除」を行うとした一方、自民党と公明党は生活必需品の税率を低くする「軽減税率」の検討を求めた。双方ともに譲らず、導入まで時間のある「将来の問題」(民主党幹部)のため、結論を先送りする方向だ。
一方、増税に伴う自動車や住宅の取得時の負担緩和策は3党が必要との認識で一致。公明党と民主党は自動車購入時にかかる消費税と自動車取得税は二重課税にあたるとの考えで、自動車取得税の廃止も含め、年末の税制改正などで議論する見通しだ。
高価格で増税の影響が大きい住宅は住宅ローン減税の拡充が論点になる。
公明党が求めた高所得者に対する所得税の一段の増税なども、税制改正の議論に先送りされる見込みだ。
一方、景気悪化時に増税を一時停止する法案の「景気弾力条項」については、自民党が「名目3%、実質2%程度」という成長率目標を削除するよう要求。民主党は党内の増税反対派に配慮して目標を盛り込んだ経緯もあり、妥協案を探っている。
今回の3党協議は、隔たりの大きい各論を棚上げにし、国民生活へ打撃を与える増税を先行させている印象が拭えず、3党は低所得者への救済策など全体像を早急に示すことが求められそうだ。』
結局のところ予想通りの結末で面白くもなんともない話だ.解散総選挙になってどの党を選んでもやることは同じだということを証明したにすぎない.既存政党の違いは立場の違いだけで政治は何も変わらないということだ.
もはや国民の選択肢はほとんど無いも同然だ.新しいものに期待したくなるところだが,それさえも信頼に足るものかどうか疑わしい.選挙に行くのにサイコロでも持っていけばいいだろうか.
社会保障・税一体改革関連法案をめぐる15日の民主、自民、公明3党の税制分野の修正協議で、消費税増税へ向けた手続きは大詰めを迎えた。しかし、低所得者対策や自動車・住宅取得時の負担軽減策など3党間で隔たりのあるテーマについては、法案の採決を優先し、軒並み棚上げされる公算が大きい。増税ありきで結論を急ぐ姿勢に納税者からの批判も予想される。
増税時の低所得者の負担緩和策では、3党は2014年4月に消費税率を8%に引き上げた時点で、一定以下の年収の人に現金を配る「簡素な給付措置」を実施することで合意した。給付対象や金額など詳細は法案成立後に検討する方針だ。
具体論で、自民党は消費税率を5%にした1997年に低所得者らに1万円を1回限りで支給した措置を参考にするよう求めたが、公明党が「手続きは簡素でも内容はしっかりしたものであるべきだ」(幹部)と手厚い給付を要求した。民主党も複数年にわたって支給したい考えだが、バラマキになれば増税による税収増の効果が薄れる懸念もある。
税率が10%になってからの対策は、民主党が個人の所得などを一元管理する共通番号制度の本格稼働を前提に、納税額の一部を戻す「給付付き税額控除」を行うとした一方、自民党と公明党は生活必需品の税率を低くする「軽減税率」の検討を求めた。双方ともに譲らず、導入まで時間のある「将来の問題」(民主党幹部)のため、結論を先送りする方向だ。
一方、増税に伴う自動車や住宅の取得時の負担緩和策は3党が必要との認識で一致。公明党と民主党は自動車購入時にかかる消費税と自動車取得税は二重課税にあたるとの考えで、自動車取得税の廃止も含め、年末の税制改正などで議論する見通しだ。
高価格で増税の影響が大きい住宅は住宅ローン減税の拡充が論点になる。
公明党が求めた高所得者に対する所得税の一段の増税なども、税制改正の議論に先送りされる見込みだ。
一方、景気悪化時に増税を一時停止する法案の「景気弾力条項」については、自民党が「名目3%、実質2%程度」という成長率目標を削除するよう要求。民主党は党内の増税反対派に配慮して目標を盛り込んだ経緯もあり、妥協案を探っている。
今回の3党協議は、隔たりの大きい各論を棚上げにし、国民生活へ打撃を与える増税を先行させている印象が拭えず、3党は低所得者への救済策など全体像を早急に示すことが求められそうだ。』
結局のところ予想通りの結末で面白くもなんともない話だ.解散総選挙になってどの党を選んでもやることは同じだということを証明したにすぎない.既存政党の違いは立場の違いだけで政治は何も変わらないということだ.
もはや国民の選択肢はほとんど無いも同然だ.新しいものに期待したくなるところだが,それさえも信頼に足るものかどうか疑わしい.選挙に行くのにサイコロでも持っていけばいいだろうか.
『白熱電球の自粛要請 政府 製造販売LED転換促す
経済産業、環境両省は、発光ダイオード(LED)電球など節電効果の高い照明への切り替えを加速させる。地球温暖化対策や夏場の電力不足に備えるためで、十三日に電力消費の多い白熱電球の製造、販売の自粛を関係業界に要請した。
政府は二〇〇八年に白熱電球の製造を一二年までにやめるよう業界に要請している。今回の要請は小売業界による販売を含め、切り替えを前倒しする狙いもある。
この日のメーカー、家電量販店など八十四社・団体との会合で、横光克彦環境副大臣が「照明は節電余地が大きい分野だ」と述べて両省大臣名の要請文を渡し、業界側は「参加団体、企業の力を合わせて要請に応えたい」と受け入れた。政府として、消費者にLED電球の購入を呼び掛けるキャンペーンも展開する。
大手メーカーでは、パナソニックが一二年度中に一般的な白熱電球の製造を終える計画としていたが、会合に出席した同社幹部は、終了を年内に早める方針を明らかにした。東芝、三菱電機のそれぞれのグループ会社は既に生産を中止。販売を取りやめた量販店もある。
環境省などの資料によると、LED電球は白熱電球に比べ消費電力が20%前後で済む。寿命も約四十倍、電気代など一年間のコストも大幅に低い。』
先日,クローゼットの電球をLED電球に交換して我が家の発熱電球はすべてLED電球への置換作業を終了した.ついでに自転車のヘッドライトも新型の高輝度LEDライトに交換し夜明け前の暗闇でも以前より安全に走れるようになった.
新型のライトは輝度が高いだけでなく照射範囲も広くなったので路面が非常に見やすくなった.充電池にも対応し電池を本体に内蔵した状態で充電器を接続するだけで充電が出来るし,電池残量が低下するとインジケーターが赤く点灯して知らせてくれるので非常に便利だ.
わたしはLED電球への交換で15%程度の節電を期待しているのだが,ちょうど以下のようなキャンペーンがあったので応募してみようかと思っている.これなら自分で調べなくても目標が達成出来ればQUOカードが届いて節電量がわかるというわけだ.
『 北海道電力は、一般家庭などの電気使用者が、8月と9月の電気使用量を節電すると、QUOカードが貰えるキャンペーン「みんなde節電キャンペーン」を行なう。
北海道電力は、7月23日~9月14日(8月13日~15日を除く)の期間、7%の節電目標が設定されている。
対象となるのは、北海道電力管内で、従量電灯A/従量電灯B/従量電灯C/時間帯別電灯(ドリーム8)/ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ)/3時間帯別電灯(eタイム3)を契約している使用者。
2012年8月分と9月分の電気使用量(kWh)の合計と、2011年8月分と9月分の電気使用量(kWh)の合計を比較して、7%以上の節電を達成した場合にQUOカードが貰える。QUOカードの金額は、節電率によって異なり、15%以上の節電では2,000円分、7%~15%未満の節電では1,000円分が貰える。』
経済産業、環境両省は、発光ダイオード(LED)電球など節電効果の高い照明への切り替えを加速させる。地球温暖化対策や夏場の電力不足に備えるためで、十三日に電力消費の多い白熱電球の製造、販売の自粛を関係業界に要請した。
政府は二〇〇八年に白熱電球の製造を一二年までにやめるよう業界に要請している。今回の要請は小売業界による販売を含め、切り替えを前倒しする狙いもある。
この日のメーカー、家電量販店など八十四社・団体との会合で、横光克彦環境副大臣が「照明は節電余地が大きい分野だ」と述べて両省大臣名の要請文を渡し、業界側は「参加団体、企業の力を合わせて要請に応えたい」と受け入れた。政府として、消費者にLED電球の購入を呼び掛けるキャンペーンも展開する。
大手メーカーでは、パナソニックが一二年度中に一般的な白熱電球の製造を終える計画としていたが、会合に出席した同社幹部は、終了を年内に早める方針を明らかにした。東芝、三菱電機のそれぞれのグループ会社は既に生産を中止。販売を取りやめた量販店もある。
環境省などの資料によると、LED電球は白熱電球に比べ消費電力が20%前後で済む。寿命も約四十倍、電気代など一年間のコストも大幅に低い。』
先日,クローゼットの電球をLED電球に交換して我が家の発熱電球はすべてLED電球への置換作業を終了した.ついでに自転車のヘッドライトも新型の高輝度LEDライトに交換し夜明け前の暗闇でも以前より安全に走れるようになった.
新型のライトは輝度が高いだけでなく照射範囲も広くなったので路面が非常に見やすくなった.充電池にも対応し電池を本体に内蔵した状態で充電器を接続するだけで充電が出来るし,電池残量が低下するとインジケーターが赤く点灯して知らせてくれるので非常に便利だ.
わたしはLED電球への交換で15%程度の節電を期待しているのだが,ちょうど以下のようなキャンペーンがあったので応募してみようかと思っている.これなら自分で調べなくても目標が達成出来ればQUOカードが届いて節電量がわかるというわけだ.
『 北海道電力は、一般家庭などの電気使用者が、8月と9月の電気使用量を節電すると、QUOカードが貰えるキャンペーン「みんなde節電キャンペーン」を行なう。
北海道電力は、7月23日~9月14日(8月13日~15日を除く)の期間、7%の節電目標が設定されている。
対象となるのは、北海道電力管内で、従量電灯A/従量電灯B/従量電灯C/時間帯別電灯(ドリーム8)/ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ)/3時間帯別電灯(eタイム3)を契約している使用者。
2012年8月分と9月分の電気使用量(kWh)の合計と、2011年8月分と9月分の電気使用量(kWh)の合計を比較して、7%以上の節電を達成した場合にQUOカードが貰える。QUOカードの金額は、節電率によって異なり、15%以上の節電では2,000円分、7%~15%未満の節電では1,000円分が貰える。』
『測定地選定にSPEEDI利用=原発事故時、非公表の一方で―文科省
東京電力福島第1原発事故で、福島県飯舘村など北西方面に放射能汚染が広がった昨年3月15日の夜、文部科学省が緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の予測結果を利用して、放射線測定(モニタリング)の場所を選定していたことが11日、同省への取材で分かった。
当時、SPEEDIは原発からの放出源情報が得られず、文科省は「実際のデータに基づく予測と異なる」として公表していなかったが、同省自身はこの結果をモニタリング地域の選定に利用していたことになる。』
言っていることとやっている事が一致していない.放射線量を測定しSPEEDIの予測の検証でもしようとしていたのだろうか.何が大事かという事がわかってないのか,それとも国民の健康なんて知ったことじゃないのか.
誰のために仕事するのかわかってない官僚たちに税金を使うなんて無駄だとしか思えない.
東京電力福島第1原発事故で、福島県飯舘村など北西方面に放射能汚染が広がった昨年3月15日の夜、文部科学省が緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の予測結果を利用して、放射線測定(モニタリング)の場所を選定していたことが11日、同省への取材で分かった。
当時、SPEEDIは原発からの放出源情報が得られず、文科省は「実際のデータに基づく予測と異なる」として公表していなかったが、同省自身はこの結果をモニタリング地域の選定に利用していたことになる。』
言っていることとやっている事が一致していない.放射線量を測定しSPEEDIの予測の検証でもしようとしていたのだろうか.何が大事かという事がわかってないのか,それとも国民の健康なんて知ったことじゃないのか.
誰のために仕事するのかわかってない官僚たちに税金を使うなんて無駄だとしか思えない.
『東電公聴会 怒る参加者 「ガス抜きだ」人件費に批判集中
東京電力の家庭向け電気料金の値上げをめぐり、七日に経済産業省で開かれた公聴会。一般利用者の声を国や東電に直接届ける唯一の舞台にもかかわらず、東電の言い訳やはぐらかしが目立ち、経産省側は回答の先送りに終始した。結局、やりとりはかみ合わず、意見を述べた参加者からは「利用者の不満のガス抜きに利用されただけ」との冷めた声も聞かれた。
公聴会では一般の利用者十人と、経産省が依頼した消費者団体や中小企業団体の代表ら十人が意見を述べた。値上げを全面的に容認する声は一握りで、徹底した経費削減の取り組みがない中での値上げには反対という意見が大勢を占めた。
特に人件費をめぐっては、削減後に大企業平均年収(五百四十三万円)を下回るのは二〇一二年度だけで、一三年度以降は約五百七十万円とする点に批判が集中。東電の西沢俊夫社長は「社員20%、管理職25%のカットは続ける」と釈明したが、公的支援を受ける企業として適切かどうかについては言及を避けた。
料金の原価計算の前提に、一三年四月からの柏崎刈羽原発の再稼働を盛り込んだ点にも反対が相次いだ。元東電社員の鈴木章治さん(72)=神奈川県横須賀市=は「原発は危険と声を上げた社員は社内で差別を受けた。安全神話に固執し反省もなく、原発再稼働を前提とする値上げには反対だ」と東電の内情を交えて訴えた。
西沢社長は「安全と地元の理解が大前提だ。決して再稼働ありきではない」と繰り返す一方で、「電力の安定供給には原発は必要だ」と再稼働に固執する姿勢ものぞかせた。
一方、経産省側は回答の先送りに終始。利用者の質問に、資源エネルギー庁の蓮井智哉企画官が「第三者の電気料金審査専門委員会で検討する」と何度も連発したため、会場から「同じことばかり言うな」とヤジが飛ぶ場面もあった。
公聴会を東京と埼玉での二回しか開かない経産省の運営にも「あまりに拙速で、利用者をないがしろにしている」(山梨県消費者団体連絡協議会の斉藤いずみ事務局長)との批判が出た。
意見陳述した東京都杉並区の元高校教諭山崎嘉永さん(79)は公聴会後、「結局、利用者のガス抜き大会だった。経産省も東電も『検討します』の回答で、不満を言わせているだけ。こんな公聴会なら何回やっても同じだ」と話し、公聴会の存在意義に疑問を呈した。
<公聴会> 国民生活にかかわる重要政策について、申し込みのあった国民から意見を聞いて、政策に反映させる場。電気料金を改定する際には、経済産業相は公聴会を開いて、広く一般から意見を聞くことを、電気事業法で定めている。東京電力の電気料金の値上げ申請をめぐり公聴会が開かれるのは1980年以来、32年ぶり。公聴会での意見は今後、枝野幸男経産相が値上げの可否を判断する際に参考にする、とされている。』
何の事はない,法律で公聴会を開くことが定められているからやっただけということだろう.電力会社の住民説明会には社員を出席させて賛成意見を言わせていたくらいだから,形だけの公聴会なんてお手のものだろう.
挙句に自分の会社の都合ばかり並べ,徹底的な合理化なんて嘘を平気で言ってのけるのも未だに電力会社がなければ困るのは国民だという上から目線を変える気が毛頭無いことの証だろう.
やはり東電はまるごと国有化して給与も賠償金を全部払い終わって黒字になるまではカットした上で発電と送電の会社に分割し,さらに携帯電話のように同一エリアで2つ以上の電力会社が競争するような環境をつくらないと適正なサービスを提供するまともな会社にはならないだろう.
消費税問題も電力問題も結局のところ国民の立場で考える気など皆無で,最初に増税,値上げ,再稼働が決めてあり,後は各党の政治家たちで議論しているふりをして国民の顔色を見ながら強引に国民を言いくるめようとしているにすぎないのではないだろうか.もちろん背後には官僚天国を作り上げてきた財務省がいることは疑う余地もないのだろうが.
東京電力の家庭向け電気料金の値上げをめぐり、七日に経済産業省で開かれた公聴会。一般利用者の声を国や東電に直接届ける唯一の舞台にもかかわらず、東電の言い訳やはぐらかしが目立ち、経産省側は回答の先送りに終始した。結局、やりとりはかみ合わず、意見を述べた参加者からは「利用者の不満のガス抜きに利用されただけ」との冷めた声も聞かれた。
公聴会では一般の利用者十人と、経産省が依頼した消費者団体や中小企業団体の代表ら十人が意見を述べた。値上げを全面的に容認する声は一握りで、徹底した経費削減の取り組みがない中での値上げには反対という意見が大勢を占めた。
特に人件費をめぐっては、削減後に大企業平均年収(五百四十三万円)を下回るのは二〇一二年度だけで、一三年度以降は約五百七十万円とする点に批判が集中。東電の西沢俊夫社長は「社員20%、管理職25%のカットは続ける」と釈明したが、公的支援を受ける企業として適切かどうかについては言及を避けた。
料金の原価計算の前提に、一三年四月からの柏崎刈羽原発の再稼働を盛り込んだ点にも反対が相次いだ。元東電社員の鈴木章治さん(72)=神奈川県横須賀市=は「原発は危険と声を上げた社員は社内で差別を受けた。安全神話に固執し反省もなく、原発再稼働を前提とする値上げには反対だ」と東電の内情を交えて訴えた。
西沢社長は「安全と地元の理解が大前提だ。決して再稼働ありきではない」と繰り返す一方で、「電力の安定供給には原発は必要だ」と再稼働に固執する姿勢ものぞかせた。
一方、経産省側は回答の先送りに終始。利用者の質問に、資源エネルギー庁の蓮井智哉企画官が「第三者の電気料金審査専門委員会で検討する」と何度も連発したため、会場から「同じことばかり言うな」とヤジが飛ぶ場面もあった。
公聴会を東京と埼玉での二回しか開かない経産省の運営にも「あまりに拙速で、利用者をないがしろにしている」(山梨県消費者団体連絡協議会の斉藤いずみ事務局長)との批判が出た。
意見陳述した東京都杉並区の元高校教諭山崎嘉永さん(79)は公聴会後、「結局、利用者のガス抜き大会だった。経産省も東電も『検討します』の回答で、不満を言わせているだけ。こんな公聴会なら何回やっても同じだ」と話し、公聴会の存在意義に疑問を呈した。
<公聴会> 国民生活にかかわる重要政策について、申し込みのあった国民から意見を聞いて、政策に反映させる場。電気料金を改定する際には、経済産業相は公聴会を開いて、広く一般から意見を聞くことを、電気事業法で定めている。東京電力の電気料金の値上げ申請をめぐり公聴会が開かれるのは1980年以来、32年ぶり。公聴会での意見は今後、枝野幸男経産相が値上げの可否を判断する際に参考にする、とされている。』
何の事はない,法律で公聴会を開くことが定められているからやっただけということだろう.電力会社の住民説明会には社員を出席させて賛成意見を言わせていたくらいだから,形だけの公聴会なんてお手のものだろう.
挙句に自分の会社の都合ばかり並べ,徹底的な合理化なんて嘘を平気で言ってのけるのも未だに電力会社がなければ困るのは国民だという上から目線を変える気が毛頭無いことの証だろう.
やはり東電はまるごと国有化して給与も賠償金を全部払い終わって黒字になるまではカットした上で発電と送電の会社に分割し,さらに携帯電話のように同一エリアで2つ以上の電力会社が競争するような環境をつくらないと適正なサービスを提供するまともな会社にはならないだろう.
消費税問題も電力問題も結局のところ国民の立場で考える気など皆無で,最初に増税,値上げ,再稼働が決めてあり,後は各党の政治家たちで議論しているふりをして国民の顔色を見ながら強引に国民を言いくるめようとしているにすぎないのではないだろうか.もちろん背後には官僚天国を作り上げてきた財務省がいることは疑う余地もないのだろうが.
『東電値上げに「既得権による甘え」の声
東京電力が申請した家庭向けの電気料金の値上げに関して、一般利用者からの意見を聴く経済産業省主催の公聴会が7日、経産省内で開かれた。公聴会は利用者が直接意見を表明できる唯一の場。東電は平均10・28%の値上げを求めているが、多くの利用者から厳しい声が上がった。
事前に申し込んだ利用者10人がそれぞれ、東電の西沢俊夫社長らに値上げの理由をただしたり、意見や質問を述べたりした。
意見陳述した塚田悟さんは「東電の経費削減努力は不十分で、値上げは地域独占の既得権による甘え。消費者を無視した体質の改善が重要だ」と指摘。値上げの前提として、さらなる人件費削減や、発電部門と送電部門を分ける発送電分離による競争促進を求めた。
西沢社長は「徹底した合理化を進めているが、燃料費の増加をまかなうことは非常に難しい」と釈明した。
静岡市沼津市の学習塾経営工藤崇さん(48)は「原発は絶対に安全と言いながら福島の事故を起こした国や電力会社などの『原子力ムラ』が責任を取ることが、値上げを認める条件だ」と述べ、原発推進政策の見直しを求めた。
東京都板橋区の翻訳会社経営坂井正明さん(54)は「家庭向けで9割を稼ぐ利益構造や、大企業平均より高い給与水準を維持するなら、国民感情として値上げを受け入れるのは難しい」と反対を表明した。
午後からは、消費者団体や中小企業団体の代表者ら計10人が意見を述べる。公聴会での意見は、枝野幸男経産相が値上げの可否を最終判断する際の参考にする。
経産省は当初、一日あたり50~70人の参加を見込んでいたが、東京は平日開催であることなどから大幅に下回った。インターネットを通じた意見募集には615件(4日現在)が寄せられている。公聴会は9日にも、さいたま市で開かれる。
東電は福島第1原発事故に伴う原発の停止で、火力発電用の燃料費が急増し、経費削減しても年間約6700億円が不足するとして7月からの値上げを経産省に申請している。』
燃料費の高騰というが,米国で地下の岩盤にあるシェールガスが採取されるようになって天然ガスの価格は大きく下がりこの4月には1.8ドルだったのに,日本は中東や東南アジアの産油国から調達し,価格も石油価格に連動するという不利な契約で昨年は概ね18ドルと国際相場の10倍の価格で買っていたそうだ.
半額で調達する努力をすれば8000億円近くが浮く計算になりそれだけで電気料金を値上げしなくても済むそうだ.そして,原価計算の内訳を分析すると賠償金以外の事故関係費用がこっそり算入されていて少なくとも1332億円が「委託費」などの名目で値上げ料金の中に含まれているらしい.
さらに原発は停止しているときのほうがコストがかかり,原発関係費用を合計すると約3600億円となり東電が今回の値上げで調達する年間6000億円以上の資金のおよそ6割は実は燃料費などではなく原発のために使われる「再稼働準備金」という話もある.
要するに,東電は原発を動かさないと経費がかさむから電気料金は高くなると国民に思い込ませようとしているだけであり,最初から徹底的な経費削減をする気などさらさら無いということだろう.現に重大事故を起こしたのに大企業平均より高い給与水準を維持するというのだから社会的責任などきっと微塵も感じていないのだ.
もっとも,東電にすれば国策に従って原子力安全委員会の言う通りの作文までしてあげたのだから自分たちの責任ではないと言いたいのかもしれないが,こんな企業に税金を投入しさらに電気料金も値上げされるなんてなんと馬鹿らしい話だと思うのは私だけではないだろう.
東京電力が申請した家庭向けの電気料金の値上げに関して、一般利用者からの意見を聴く経済産業省主催の公聴会が7日、経産省内で開かれた。公聴会は利用者が直接意見を表明できる唯一の場。東電は平均10・28%の値上げを求めているが、多くの利用者から厳しい声が上がった。
事前に申し込んだ利用者10人がそれぞれ、東電の西沢俊夫社長らに値上げの理由をただしたり、意見や質問を述べたりした。
意見陳述した塚田悟さんは「東電の経費削減努力は不十分で、値上げは地域独占の既得権による甘え。消費者を無視した体質の改善が重要だ」と指摘。値上げの前提として、さらなる人件費削減や、発電部門と送電部門を分ける発送電分離による競争促進を求めた。
西沢社長は「徹底した合理化を進めているが、燃料費の増加をまかなうことは非常に難しい」と釈明した。
静岡市沼津市の学習塾経営工藤崇さん(48)は「原発は絶対に安全と言いながら福島の事故を起こした国や電力会社などの『原子力ムラ』が責任を取ることが、値上げを認める条件だ」と述べ、原発推進政策の見直しを求めた。
東京都板橋区の翻訳会社経営坂井正明さん(54)は「家庭向けで9割を稼ぐ利益構造や、大企業平均より高い給与水準を維持するなら、国民感情として値上げを受け入れるのは難しい」と反対を表明した。
午後からは、消費者団体や中小企業団体の代表者ら計10人が意見を述べる。公聴会での意見は、枝野幸男経産相が値上げの可否を最終判断する際の参考にする。
経産省は当初、一日あたり50~70人の参加を見込んでいたが、東京は平日開催であることなどから大幅に下回った。インターネットを通じた意見募集には615件(4日現在)が寄せられている。公聴会は9日にも、さいたま市で開かれる。
東電は福島第1原発事故に伴う原発の停止で、火力発電用の燃料費が急増し、経費削減しても年間約6700億円が不足するとして7月からの値上げを経産省に申請している。』
燃料費の高騰というが,米国で地下の岩盤にあるシェールガスが採取されるようになって天然ガスの価格は大きく下がりこの4月には1.8ドルだったのに,日本は中東や東南アジアの産油国から調達し,価格も石油価格に連動するという不利な契約で昨年は概ね18ドルと国際相場の10倍の価格で買っていたそうだ.
半額で調達する努力をすれば8000億円近くが浮く計算になりそれだけで電気料金を値上げしなくても済むそうだ.そして,原価計算の内訳を分析すると賠償金以外の事故関係費用がこっそり算入されていて少なくとも1332億円が「委託費」などの名目で値上げ料金の中に含まれているらしい.
さらに原発は停止しているときのほうがコストがかかり,原発関係費用を合計すると約3600億円となり東電が今回の値上げで調達する年間6000億円以上の資金のおよそ6割は実は燃料費などではなく原発のために使われる「再稼働準備金」という話もある.
要するに,東電は原発を動かさないと経費がかさむから電気料金は高くなると国民に思い込ませようとしているだけであり,最初から徹底的な経費削減をする気などさらさら無いということだろう.現に重大事故を起こしたのに大企業平均より高い給与水準を維持するというのだから社会的責任などきっと微塵も感じていないのだ.
もっとも,東電にすれば国策に従って原子力安全委員会の言う通りの作文までしてあげたのだから自分たちの責任ではないと言いたいのかもしれないが,こんな企業に税金を投入しさらに電気料金も値上げされるなんてなんと馬鹿らしい話だと思うのは私だけではないだろう.
『全電源喪失「考慮は不要」、安全委が東電・関電に作文指示
原子力発電所で長時間の全電源喪失を「考慮する必要はない」とした国の安全設計審査指針について、1992年に原子力安全委員会が東京電力と関西電力に対し、改正は不要という報告書案の作成を指示していたことが、4日わかった。安全委は東電案を報告書に採用し、指針改正を見送っていた。
当時、適切に指針を改正して対策を取っていれば、福島第1原発事故を防げた可能性もある。班目春樹委員長は4日に記者会見し「今から考えると不適切なことをやっていた」と当時の安全委の対応を批判した。
指針を見直すかどうかの資料の情報公開請求を受けた安全委は、昨年10月に「全ての文書」と称してホームページに載せたが、東電などに指示した文書は含まれていなかった。国会の事故調査委員会が全資料を公表するよう2度にわたって要求し、安全委は4日に資料を公表した。
安全委事務局は「文書の存在は知っていたが、昨年10月に全部出したと思い込み、公表を失念していた」と説明した。
公表した92年10月の報告書骨子(案)には「原稿担当」として「事務局」「電力」が並び、報告書の章ごとに誰が分担する予定かを記載。安全委が電力会社に送った文書では「中長時間の全電源喪失を考えなくて良い理由を作文して下さい」と指示。東電からの回答文書には「これでOK」との書き込みがあった。』
『全電源喪失、「対策不要」業界に作文指示、指針改定見送り 放射能漏れ
東京電力福島第1原発事故の原因となった長時間の全電源喪失について、国の原子力安全委員会の作業部会が平成4年、対策が不要な理由を文書で作成するよう電力業界側に指示し、東電が作成した文章をほぼ丸写しした報告書をまとめ、安全指針の改定を見送っていたことが3日、分かった。安全委は事実関係を隠蔽(いんぺい)してきたが、国会事故調査委員会が受理した同部会の内部資料で判明。規制当局側が業界側と癒着し、不適切な指針を容認してきた実態が明らかになった。
この作業部会は「全交流電源喪失事象検討ワーキンググループ」。海外で全電源喪失の事例が起きたことを受けて3年に設置され、有識者の専門委員のほか東電、関西電力、日本原子力研究所(当時)の外部関係者が参加した。
長時間の全電源喪失は原発の過酷事故につながる重大事態だが、2年に策定された国の安全設計審査指針は「長時間(30分程度以上)の全電源喪失は考慮する必要はない」としており、作業部会はこの妥当性について非公開の会議を開き検討した。
会議では、全電源喪失対策を指針に盛り込むことについて、関電が「指針への反映は行き過ぎ」、東電が「(過酷事故の)リスクが特に高いとは思われない」と反発。新たに対策が必要になると設備などでコストが増えるためとみられる。
これに応じる形で作業部会は4年10月、当時の安全委事務局だった科学技術庁原子力安全調査室経由で、東電と関電に「今後も長時間の全電源喪失を考えなくて良い理由を作文してください」と文書で指示。規制当局の安全委が、規制方針にかかわる文書作成を業界側に丸投げした格好だ。
これに対し東電は同年11月、「わが国の原発は米国の基準に比べると設計の余裕があり、十分な安全性が確保される」などと回答。報告書案にほぼそのまま盛り込まれ、5年6月に「重大な事態に至る可能性は低い」とする最終報告書が作成され、指針の見直しは見送られた。
安全委は福島第1原発事故を受け昨年7月、作業部会の議事などを公表し、関連資料はすべてホームページで公開したとしていた。しかし、全電源喪失の対策が不備だった経緯を調査している国会事故調が今年に入って、業界側とのやりとりを示す内部資料が隠蔽されている可能性を安全委に指摘、提出を求めていた。
原発の全電源喪失 原発に送電線経由で送られる外部電源と、ディーゼル発電機などの非常用電源がともに失われる緊急事態。国の安全設計審査指針では国内の原発で発生しても30分程度で復旧するとされ、長時間の発生は考慮する必要はないとされていた。しかし、東京電力福島第1原発事故で長期間にわたり発生し、原子炉の冷却機能が失われ炉心溶融などの深刻な事態を招いた。』
またしても隠蔽.そして,『国の原子力安全委員会の作業部会が平成4年、対策が不要な理由を文書で作成するよう電力業界側に指示し、東電が作成した文章をほぼ丸写しした報告書』というのは規制当局側が業界側と癒着していた証拠だろう.
こんな話ばかり続いて呆れるばかりだが,こんなことをしても誰も罪に問われないのだからこれからつくるという原子力規制庁もあまりあてには出来ないだろう.
「今から考えると不適切なことをやっていた」,「文書の存在は知っていたが、昨年10月に全部出したと思い込み、公表を失念していた」というのも何だかいい加減聞き飽きた言い分だ.
見えない所で不正をはたらき,問題は出来る限り隠蔽し,バレると自分のやったことを誤摩化して正当化しようとする.日本がダメなのはこういう不正のツケが溜まってきたからなのだろう.こんな連中にたくさんの税金が使われて,今度はそのツケが国民に回ってきて大増税というのだからこの国の政治は腐り切っていたということだろう.
原子力発電所で長時間の全電源喪失を「考慮する必要はない」とした国の安全設計審査指針について、1992年に原子力安全委員会が東京電力と関西電力に対し、改正は不要という報告書案の作成を指示していたことが、4日わかった。安全委は東電案を報告書に採用し、指針改正を見送っていた。
当時、適切に指針を改正して対策を取っていれば、福島第1原発事故を防げた可能性もある。班目春樹委員長は4日に記者会見し「今から考えると不適切なことをやっていた」と当時の安全委の対応を批判した。
指針を見直すかどうかの資料の情報公開請求を受けた安全委は、昨年10月に「全ての文書」と称してホームページに載せたが、東電などに指示した文書は含まれていなかった。国会の事故調査委員会が全資料を公表するよう2度にわたって要求し、安全委は4日に資料を公表した。
安全委事務局は「文書の存在は知っていたが、昨年10月に全部出したと思い込み、公表を失念していた」と説明した。
公表した92年10月の報告書骨子(案)には「原稿担当」として「事務局」「電力」が並び、報告書の章ごとに誰が分担する予定かを記載。安全委が電力会社に送った文書では「中長時間の全電源喪失を考えなくて良い理由を作文して下さい」と指示。東電からの回答文書には「これでOK」との書き込みがあった。』
『全電源喪失、「対策不要」業界に作文指示、指針改定見送り 放射能漏れ
東京電力福島第1原発事故の原因となった長時間の全電源喪失について、国の原子力安全委員会の作業部会が平成4年、対策が不要な理由を文書で作成するよう電力業界側に指示し、東電が作成した文章をほぼ丸写しした報告書をまとめ、安全指針の改定を見送っていたことが3日、分かった。安全委は事実関係を隠蔽(いんぺい)してきたが、国会事故調査委員会が受理した同部会の内部資料で判明。規制当局側が業界側と癒着し、不適切な指針を容認してきた実態が明らかになった。
この作業部会は「全交流電源喪失事象検討ワーキンググループ」。海外で全電源喪失の事例が起きたことを受けて3年に設置され、有識者の専門委員のほか東電、関西電力、日本原子力研究所(当時)の外部関係者が参加した。
長時間の全電源喪失は原発の過酷事故につながる重大事態だが、2年に策定された国の安全設計審査指針は「長時間(30分程度以上)の全電源喪失は考慮する必要はない」としており、作業部会はこの妥当性について非公開の会議を開き検討した。
会議では、全電源喪失対策を指針に盛り込むことについて、関電が「指針への反映は行き過ぎ」、東電が「(過酷事故の)リスクが特に高いとは思われない」と反発。新たに対策が必要になると設備などでコストが増えるためとみられる。
これに応じる形で作業部会は4年10月、当時の安全委事務局だった科学技術庁原子力安全調査室経由で、東電と関電に「今後も長時間の全電源喪失を考えなくて良い理由を作文してください」と文書で指示。規制当局の安全委が、規制方針にかかわる文書作成を業界側に丸投げした格好だ。
これに対し東電は同年11月、「わが国の原発は米国の基準に比べると設計の余裕があり、十分な安全性が確保される」などと回答。報告書案にほぼそのまま盛り込まれ、5年6月に「重大な事態に至る可能性は低い」とする最終報告書が作成され、指針の見直しは見送られた。
安全委は福島第1原発事故を受け昨年7月、作業部会の議事などを公表し、関連資料はすべてホームページで公開したとしていた。しかし、全電源喪失の対策が不備だった経緯を調査している国会事故調が今年に入って、業界側とのやりとりを示す内部資料が隠蔽されている可能性を安全委に指摘、提出を求めていた。
原発の全電源喪失 原発に送電線経由で送られる外部電源と、ディーゼル発電機などの非常用電源がともに失われる緊急事態。国の安全設計審査指針では国内の原発で発生しても30分程度で復旧するとされ、長時間の発生は考慮する必要はないとされていた。しかし、東京電力福島第1原発事故で長期間にわたり発生し、原子炉の冷却機能が失われ炉心溶融などの深刻な事態を招いた。』
またしても隠蔽.そして,『国の原子力安全委員会の作業部会が平成4年、対策が不要な理由を文書で作成するよう電力業界側に指示し、東電が作成した文章をほぼ丸写しした報告書』というのは規制当局側が業界側と癒着していた証拠だろう.
こんな話ばかり続いて呆れるばかりだが,こんなことをしても誰も罪に問われないのだからこれからつくるという原子力規制庁もあまりあてには出来ないだろう.
「今から考えると不適切なことをやっていた」,「文書の存在は知っていたが、昨年10月に全部出したと思い込み、公表を失念していた」というのも何だかいい加減聞き飽きた言い分だ.
見えない所で不正をはたらき,問題は出来る限り隠蔽し,バレると自分のやったことを誤摩化して正当化しようとする.日本がダメなのはこういう不正のツケが溜まってきたからなのだろう.こんな連中にたくさんの税金が使われて,今度はそのツケが国民に回ってきて大増税というのだからこの国の政治は腐り切っていたということだろう.
『検事ら5人前後処分へ 当時の特捜部長含め
小沢一郎・民主党元代表の政治資金規正法違反事件を巡り、東京地検特捜部で「虚偽」の捜査報告書が作成された問題で、法務・検察当局は担当検事と上司らを処分する方針を固めた。当時の地検幹部らには監督責任があるとみており、行政上の処分対象は5人前後になるとみられる。処分に合わせ、近く改善策もまとめる見通し。
10年4月、東京第5検察審査会は元代表を「起訴すべきだ」とする最初の議決を行い、再捜査を求めた。同5月、田代政弘検事が元秘書で衆議院議員の石川知裕被告を再聴取し報告書を作成したが、石川議員の「隠し録音」とは異なるやり取りがあった。この「虚偽」報告書は、上司が別に作成した5通の報告書と共に検察審に送られた。
検察関係者によると、田代検事は再聴取の際、報告書作成を予期せず、メモもとっていなかった。内部調査に「再聴取後、問答形式で報告書を作ることになり、(数カ月前の)逮捕・勾留中のやり取りとごちゃごちゃになった」と述べ、故意の虚偽記載を否定しているとされる。
上司の報告書の調査では、佐久間達哉特捜部長(当時)が元代表の供述部分などに下線を引いていたことが判明した。だが、佐久間前部長は「再捜査内容を分かりやすく説明するためだった」などと主張。強制起訴制度を盛り込んだ検察審査会法の改正を受け最高検も09年4月、再捜査の要点を検察審に分かりやすく伝えることなどを求める通達を出しており「前部長らの対応は通達の趣旨から逸脱したとはいえない」(検察首脳)と結論づける模様だ。
ただし、法務・検察当局は、最初の議決を受けた再捜査の在り方や、通常は内部向けにとどまるとされる捜査報告書の作成方法などについて、担当検事と特捜部幹部、地検幹部などの間に意思統一ができていなかった点を問題視。田代検事を懲戒処分とし、当時の部長や副部長らにも一定の処分を下す方向で調整している。改善策として▽議決を受けた再捜査にはそれまでとは別の検事を加える▽検察審向けの提出資料は捜査に関与していない検事もチェックする--などのルール化を検討している。』
『小川前法相:指揮権発動を首相に相談 「虚偽」捜査報告で
4日の内閣改造で再任されなかった小川敏夫・前法相は同日午後、法務省内で退任の記者会見に臨み、小沢一郎・民主党元代表の陸山会事件に絡んで東京地検特捜部の元検事が「虚偽」の捜査報告書を作成したとされる問題で「野田佳彦首相に指揮権の発動を相談したが了承されなかった」と発言した。
会見で小川前法相は検察当局が元特捜部検事を不起訴にする方針と報道されたことなどを受け「部内の事件に対する捜査が消極的と感じた。法相が指揮権を発動するにふさわしい事案だと感じた」と述べ、5月下旬に官邸に赴いて野田首相に相談したことを明らかにした。
指揮権発動の相談と法相として再任されなかったことの関係については「想像で言うわけにはいかないので分からない」と話した。
検察庁法は指揮権について「法相は個々の事件の取り調べや処分については、検事総長のみを指揮することができる」と定めている。過去には指揮権を肯定した法相もいたが、 個々の事件に関して法相が指揮するのは司法に対する政治的介入になりかねない、として否定的な見方も根強い。』
検察の虚偽報告書で検察審査会を起訴に誘導し,官僚機構にメスを入れようとする小沢氏の政治活動を妨害すれば財務省から何らかの見返りがあったかもしれないという推理はどうだろうか.
反小沢の市民感情が本当に検察審査会にあったかどうかも興味があるところだが,小沢氏側に決定的な証拠がないのに起訴されるのとは対照的に,虚偽報告書という立派な証拠があるにもかかわらず検察官は起訴されないというのだから日本が法治国家というのも虚偽ではないだろうか.
すべては中央集権の官僚機構と政権側の政治家の都合で決められ,それに同調するマスコミとで国民の目を欺く仕組みが戦前戦後を通して完成されてきたのだろう.国民は正しい情報を何も知らされないままマスコミの誘導に従ってつくられたものを世論だと思うしかないのだろうか.
今起きていることを考えれば,この一件は財務省と野田首相による大増税のための布石だったような気がするのは私だけだろうか.
小沢一郎・民主党元代表の政治資金規正法違反事件を巡り、東京地検特捜部で「虚偽」の捜査報告書が作成された問題で、法務・検察当局は担当検事と上司らを処分する方針を固めた。当時の地検幹部らには監督責任があるとみており、行政上の処分対象は5人前後になるとみられる。処分に合わせ、近く改善策もまとめる見通し。
10年4月、東京第5検察審査会は元代表を「起訴すべきだ」とする最初の議決を行い、再捜査を求めた。同5月、田代政弘検事が元秘書で衆議院議員の石川知裕被告を再聴取し報告書を作成したが、石川議員の「隠し録音」とは異なるやり取りがあった。この「虚偽」報告書は、上司が別に作成した5通の報告書と共に検察審に送られた。
検察関係者によると、田代検事は再聴取の際、報告書作成を予期せず、メモもとっていなかった。内部調査に「再聴取後、問答形式で報告書を作ることになり、(数カ月前の)逮捕・勾留中のやり取りとごちゃごちゃになった」と述べ、故意の虚偽記載を否定しているとされる。
上司の報告書の調査では、佐久間達哉特捜部長(当時)が元代表の供述部分などに下線を引いていたことが判明した。だが、佐久間前部長は「再捜査内容を分かりやすく説明するためだった」などと主張。強制起訴制度を盛り込んだ検察審査会法の改正を受け最高検も09年4月、再捜査の要点を検察審に分かりやすく伝えることなどを求める通達を出しており「前部長らの対応は通達の趣旨から逸脱したとはいえない」(検察首脳)と結論づける模様だ。
ただし、法務・検察当局は、最初の議決を受けた再捜査の在り方や、通常は内部向けにとどまるとされる捜査報告書の作成方法などについて、担当検事と特捜部幹部、地検幹部などの間に意思統一ができていなかった点を問題視。田代検事を懲戒処分とし、当時の部長や副部長らにも一定の処分を下す方向で調整している。改善策として▽議決を受けた再捜査にはそれまでとは別の検事を加える▽検察審向けの提出資料は捜査に関与していない検事もチェックする--などのルール化を検討している。』
『小川前法相:指揮権発動を首相に相談 「虚偽」捜査報告で
4日の内閣改造で再任されなかった小川敏夫・前法相は同日午後、法務省内で退任の記者会見に臨み、小沢一郎・民主党元代表の陸山会事件に絡んで東京地検特捜部の元検事が「虚偽」の捜査報告書を作成したとされる問題で「野田佳彦首相に指揮権の発動を相談したが了承されなかった」と発言した。
会見で小川前法相は検察当局が元特捜部検事を不起訴にする方針と報道されたことなどを受け「部内の事件に対する捜査が消極的と感じた。法相が指揮権を発動するにふさわしい事案だと感じた」と述べ、5月下旬に官邸に赴いて野田首相に相談したことを明らかにした。
指揮権発動の相談と法相として再任されなかったことの関係については「想像で言うわけにはいかないので分からない」と話した。
検察庁法は指揮権について「法相は個々の事件の取り調べや処分については、検事総長のみを指揮することができる」と定めている。過去には指揮権を肯定した法相もいたが、 個々の事件に関して法相が指揮するのは司法に対する政治的介入になりかねない、として否定的な見方も根強い。』
検察の虚偽報告書で検察審査会を起訴に誘導し,官僚機構にメスを入れようとする小沢氏の政治活動を妨害すれば財務省から何らかの見返りがあったかもしれないという推理はどうだろうか.
反小沢の市民感情が本当に検察審査会にあったかどうかも興味があるところだが,小沢氏側に決定的な証拠がないのに起訴されるのとは対照的に,虚偽報告書という立派な証拠があるにもかかわらず検察官は起訴されないというのだから日本が法治国家というのも虚偽ではないだろうか.
すべては中央集権の官僚機構と政権側の政治家の都合で決められ,それに同調するマスコミとで国民の目を欺く仕組みが戦前戦後を通して完成されてきたのだろう.国民は正しい情報を何も知らされないままマスコミの誘導に従ってつくられたものを世論だと思うしかないのだろうか.
今起きていることを考えれば,この一件は財務省と野田首相による大増税のための布石だったような気がするのは私だけだろうか.
あったのは安全神話だけ
2012年6月3日 社会の問題
『「15条通報」で住民避難が始まるはずだった
──当初、国は「原子炉が高温高圧になって温度計や圧力計が壊れたため、SPEEDIのデータは不正確だから公表しなかった」と説明していました。しかし「事故に備えたシステムが事故で壊れた」など矛盾した説明で、とうてい信用できませんでした。
「率直に言って、たとえSPEEDIが作動していなくても、私なら事故の規模を5秒で予測して、避難の警告を出せると思います。『過酷事故』の定義には『全電源喪失事故』が含まれているのですから、プラントが停電になって情報が途絶する事態は当然想定されています」
ここでもう、私は一発食らった気持ちだった。3.11の発生直後の印象から、原発事故は展開を予測することなど不可能だと思っていたからだ。
──どういうことでしょうか。
松野さんは全国の原発事故の対策システムを設計する責任者だった
「台風や雪崩と違って、原子力災害は100倍くらい正確に予測通りに動くんです」
──当初は福島第一原発から放出された放射性物質の量がよく分からなかったのではないのですか。それではどれくらい遠くまで逃げてよいのか分からないのではないのでしょうか。
「そんなことはありません。総量など、正確に分からなくても、大体でいいんです」
そう言って、松野さんは自著のページを繰った。そして「スリーマイル島事故」と「チェルノブイリ事故」で放出された希ガスの総量についての記述を探し出した。
「スリーマイル島事故では、5かける10の16乗ベクレルのオーダーでした。チェルノブイリ事故では5かける10の18乗のオーダーです。ということは、福島第一原発事故ではとりあえず10の17乗ベクレルの規模を想定すればいい」
「スリーマイル島事故では避難は10キロの範囲内でした。チェルノブイリでは30キロだった。ということは、福島第一原発事故ではその中間、22キロとか25キロ程度でしょう。とにかく逃がせばいいのです。私なら5秒で考えます。全交流電源を喪失したのですから、格納容器が壊れることを考えて、25時間以内に30キロの範囲の住人を逃がす」
──「全交流電源喪失」はどの時点で分かるのですか。どこから起算すればいいのですか。
「簡単です。『原子力災害対策特別措置法』第15条に定められた通り、福島第一発電所が政府に『緊急事態の通報』をしています。3月11日の午後4時45分です。このときに格納容器が壊れることを想定しなくてはいけない。つまり放射性物質が外に漏れ出すことを考えなくてはいけない。ここからが『よーい、スタート』なのです」
私はあっけにとられた。そういえばそうだ。法律はちゃんと「こうなったら周辺住民が逃げなくてはいけないような大事故ですよ」という基準を設けていて「そうなったら黙っていないで政府に知らせるのだよ」という電力会社への法的義務まで作っているのだ。「全交流電源喪失・冷却機能喪失で15条通報」イコール「格納容器の破損の恐れ」イコール「放射性物質の放出」なのだ。
そして、それは同日午後2時46分の東日本大震災発生から、わずか1時間59分で来ていたのだ。すると、この後「全交流電源喪失~放射性物質の放出」の間にある「メルトダウンがあったのか、なかったのか」という論争は、防災の観点からは、枝葉末節でしかないと分かる。
「15条通報」があった時点で「住民を被曝から守る」=「原子力防災」は始まっていなくてはならなかったのだ。
原子炉を助けようとして住民のことを忘れていた?
「甲状腺がんを防止するために子どもに安定ヨウ素剤を飲ませるのは、被曝から24時間以内でないと効果が急激に減ります。放射性物質は、風速10メートルと仮定して、1~2時間で30キロ到達します。格納容器が壊れてから飲むのでは意味がない。『壊れそうだ』の時点で飲まないといけない」
ところが、政府が原子力緊急事態宣言を出すのは午後7時3分である。2時間18分ほったらかしになったわけだ。これが痛い。
「一刻を争う」という時間感覚が官邸にはなかったのではないか、と松野さんは指摘する。そういう文脈で見ると、発生から24時間経たないうちに「現地視察」に菅直人首相が出かけたことがいかに「ピントはずれ」であるかが分かる。
──首相官邸にいた班目春樹(原子力安全委員会)委員長は「情報が入ってこなかったので、総理に助言したくでもできなかった」と言っています。SPEEDIやERSSが作動していないなら、それも一理あるのではないですか。
「いや、それは内科の医師が『内臓を見ていないから病気が診断できない』と言うようなものだ。中が分からなくても、原発災害は地震や台風より被害が予測できるものです」
「もとより、正確な情報が上がってきていれば『専門家』は必要ないでしょう。『全交流電源喪失』という情報しかないから、その意味するところを説明できる専門家が必要だったのです。専門家なら、分からないなりに25時間を割り振って、SPEEDIの予測、避難や、安定ヨウ素剤の配布服用などの指示を出すべきだったのです」
ひとこと説明を加えるなら、福島第一原発が全交流電源を失ったあと、首相官邸が必死になっていたのは「代わりの電源の用意」(電源車など)であって、住民の避難ではなかった。本欄でも報告したように、翌日3月12日午後3時前の段階で、原発から3キロの双葉厚生病院(双葉町)での避難すら完了せず、井戸川克隆町長を含む300人が1号機の水素爆発が噴き出した「死の灰」を浴びたことを思い出してほしい。
「ERSSの結果が出てくるまでの間は、SPEEDIに1ベクレルを代入して計算することになっています。そのうえで風向きを見れば、避難すべき方向だけでも分かる。私なら10の17乗ベクレルを入れます。それで住民を逃がすべき範囲も分かる」
──どうして初動が遅れたのでしょうか。
「地震で送電線が倒れても、津波が来るまでの1時間弱は非常用ディーゼル発電機が動いていたはずです。そこで東京にあるERSSは自動起動していたはずだ。このとき原発にはまだ電源があったので、予測計算はまだ正常に進展する結果を示していたでしょう。しかし、ERSSの担当者が、非常用ディーゼル発電機からの電源だけで原子炉が正常を保っている危うさを認識していれば、さらに『ディーゼル発電機も故障するかもしれない』という『全電源喪失』を想定した予測計算をしたと思います。この計算も30分でできる。私がいた時はこのような先を読んだ予測計算も訓練でやっていた。原子力安全・保安院のERSS担当部署がそれをやらさなかったのではないか。この最初の津波が来るまでの1時間弱のロスが重大だったと思う」
──すべてが後手に回っているように思えます。なぜでしょう。
「何とか廃炉を避けたいと思ったのでしょう。原子炉を助けようとして、住民のことを忘れていた。太平洋戦争末期に軍部が『戦果を挙げてから降伏しよう』とずるずる戦争を長引かせて国民を犠牲にしたのと似ています」
──廃炉にすると、1炉あたり数兆円の損害が出ると聞きます。それでためらったのではないですか。
「1号機を廃炉する決心を早くすれば、まだコストは安かった。2、3号機は助かったかもしれない。1号機の水素爆発(12日)でがれきが飛び散り、放射能レベルが高かったため2、3号機に近づけなくなって14日と15日にメルトダウンを起こした。1号機に見切りをさっさとつけるべきだったのです」
──その計算がとっさにできるものですか。
「1号機は40年経った原子炉なのですから、そろそろ廃炉だと常識で分かっていたはずです。私が所長なら『どうせ廃炉にする予定だったんだから、住民に被曝させるくらいなら廃炉にしてもかまわない』と思うでしょう。1機1兆円です。逆に、被害が拡大して3機すべてが廃炉になり、数千人が被曝する賠償コストを考えると、どうですか? 私は10秒で計算します。普段から『老朽化し、かつシビアアクシデント対策が十分でない原子炉に何かあったら廃炉にしよう』と考えておかなければならない」
このままうやむやにすると、また同じことが起きる
私にとって不思議だったのは、これほど事故を予見し尽くしていた人材が電力業界内部にいたのに、その知見が無視され、死蔵されたことだ。松野さんにとっても、自分の長年の研究と専門知識が現実の事故対策に生かされなかったことは痛恨だった。
「私の言うことは誰も聞いてくれませんでした。誰も聞いてくれないので、家で妻に話しました。しかし妻にもうるさがられる。『私の代わりにハンガーにかけたセーターにでも話していなさい』と言うのです」
松野さんはそう言って笑う。
「このままうやむやにすると、また同じことが起きるでしょう」
「広島に原爆が落とされたとき、日本政府は空襲警報を出さなかった。『一矢報いてから』と講和の条件ばかり考えていたからです。長崎の2発目は避けることができたはずなのに、しなかった。国民が犠牲にされたんです」
「負けるかもしれない、と誰も言わないのなら(電力会社も)戦争中(の軍部)と同じです。負けたとき(=最悪の原発事故が起きたとき)の選択肢を用意しておくのが、私たち学者や技術者の仕事ではないですか」
そして、松野さんはさらに驚くような話を続けた。
そもそも、日本の原発周辺の避難計画は飾りにすぎない。国は原子炉設置許可の安全評価にあたって、格納容器が破損して放射性物質が漏れ出すような事故を想定していない。もしそれを想定したら、日本では原発の立地が不可能になってしまうからだ。
そんな逆立ちした論理が政府や電力業界を支配している、というのだ。
(次回に続く)』
長いので途中からです.全文は以下にあります.
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/35339
原子力発電そのものにリスクがあるのに、あえてそれを伏せてきた国の責任は大きいし,廃炉にしてもいいような古い原子炉を助けるために住民を犠牲にするような電力会社などこれからも信用するわけにはいかない.
それなのに再稼働に向けてまた補助金ばらまきをし,それを目当てに再稼働を受け入れようとする地方自治体がいまだに存在する.やっぱりこの国には原子力発電所を安全に運用する能力のある組織とか体制がもともと存在しないということだろう.
──当初、国は「原子炉が高温高圧になって温度計や圧力計が壊れたため、SPEEDIのデータは不正確だから公表しなかった」と説明していました。しかし「事故に備えたシステムが事故で壊れた」など矛盾した説明で、とうてい信用できませんでした。
「率直に言って、たとえSPEEDIが作動していなくても、私なら事故の規模を5秒で予測して、避難の警告を出せると思います。『過酷事故』の定義には『全電源喪失事故』が含まれているのですから、プラントが停電になって情報が途絶する事態は当然想定されています」
ここでもう、私は一発食らった気持ちだった。3.11の発生直後の印象から、原発事故は展開を予測することなど不可能だと思っていたからだ。
──どういうことでしょうか。
松野さんは全国の原発事故の対策システムを設計する責任者だった
「台風や雪崩と違って、原子力災害は100倍くらい正確に予測通りに動くんです」
──当初は福島第一原発から放出された放射性物質の量がよく分からなかったのではないのですか。それではどれくらい遠くまで逃げてよいのか分からないのではないのでしょうか。
「そんなことはありません。総量など、正確に分からなくても、大体でいいんです」
そう言って、松野さんは自著のページを繰った。そして「スリーマイル島事故」と「チェルノブイリ事故」で放出された希ガスの総量についての記述を探し出した。
「スリーマイル島事故では、5かける10の16乗ベクレルのオーダーでした。チェルノブイリ事故では5かける10の18乗のオーダーです。ということは、福島第一原発事故ではとりあえず10の17乗ベクレルの規模を想定すればいい」
「スリーマイル島事故では避難は10キロの範囲内でした。チェルノブイリでは30キロだった。ということは、福島第一原発事故ではその中間、22キロとか25キロ程度でしょう。とにかく逃がせばいいのです。私なら5秒で考えます。全交流電源を喪失したのですから、格納容器が壊れることを考えて、25時間以内に30キロの範囲の住人を逃がす」
──「全交流電源喪失」はどの時点で分かるのですか。どこから起算すればいいのですか。
「簡単です。『原子力災害対策特別措置法』第15条に定められた通り、福島第一発電所が政府に『緊急事態の通報』をしています。3月11日の午後4時45分です。このときに格納容器が壊れることを想定しなくてはいけない。つまり放射性物質が外に漏れ出すことを考えなくてはいけない。ここからが『よーい、スタート』なのです」
私はあっけにとられた。そういえばそうだ。法律はちゃんと「こうなったら周辺住民が逃げなくてはいけないような大事故ですよ」という基準を設けていて「そうなったら黙っていないで政府に知らせるのだよ」という電力会社への法的義務まで作っているのだ。「全交流電源喪失・冷却機能喪失で15条通報」イコール「格納容器の破損の恐れ」イコール「放射性物質の放出」なのだ。
そして、それは同日午後2時46分の東日本大震災発生から、わずか1時間59分で来ていたのだ。すると、この後「全交流電源喪失~放射性物質の放出」の間にある「メルトダウンがあったのか、なかったのか」という論争は、防災の観点からは、枝葉末節でしかないと分かる。
「15条通報」があった時点で「住民を被曝から守る」=「原子力防災」は始まっていなくてはならなかったのだ。
原子炉を助けようとして住民のことを忘れていた?
「甲状腺がんを防止するために子どもに安定ヨウ素剤を飲ませるのは、被曝から24時間以内でないと効果が急激に減ります。放射性物質は、風速10メートルと仮定して、1~2時間で30キロ到達します。格納容器が壊れてから飲むのでは意味がない。『壊れそうだ』の時点で飲まないといけない」
ところが、政府が原子力緊急事態宣言を出すのは午後7時3分である。2時間18分ほったらかしになったわけだ。これが痛い。
「一刻を争う」という時間感覚が官邸にはなかったのではないか、と松野さんは指摘する。そういう文脈で見ると、発生から24時間経たないうちに「現地視察」に菅直人首相が出かけたことがいかに「ピントはずれ」であるかが分かる。
──首相官邸にいた班目春樹(原子力安全委員会)委員長は「情報が入ってこなかったので、総理に助言したくでもできなかった」と言っています。SPEEDIやERSSが作動していないなら、それも一理あるのではないですか。
「いや、それは内科の医師が『内臓を見ていないから病気が診断できない』と言うようなものだ。中が分からなくても、原発災害は地震や台風より被害が予測できるものです」
「もとより、正確な情報が上がってきていれば『専門家』は必要ないでしょう。『全交流電源喪失』という情報しかないから、その意味するところを説明できる専門家が必要だったのです。専門家なら、分からないなりに25時間を割り振って、SPEEDIの予測、避難や、安定ヨウ素剤の配布服用などの指示を出すべきだったのです」
ひとこと説明を加えるなら、福島第一原発が全交流電源を失ったあと、首相官邸が必死になっていたのは「代わりの電源の用意」(電源車など)であって、住民の避難ではなかった。本欄でも報告したように、翌日3月12日午後3時前の段階で、原発から3キロの双葉厚生病院(双葉町)での避難すら完了せず、井戸川克隆町長を含む300人が1号機の水素爆発が噴き出した「死の灰」を浴びたことを思い出してほしい。
「ERSSの結果が出てくるまでの間は、SPEEDIに1ベクレルを代入して計算することになっています。そのうえで風向きを見れば、避難すべき方向だけでも分かる。私なら10の17乗ベクレルを入れます。それで住民を逃がすべき範囲も分かる」
──どうして初動が遅れたのでしょうか。
「地震で送電線が倒れても、津波が来るまでの1時間弱は非常用ディーゼル発電機が動いていたはずです。そこで東京にあるERSSは自動起動していたはずだ。このとき原発にはまだ電源があったので、予測計算はまだ正常に進展する結果を示していたでしょう。しかし、ERSSの担当者が、非常用ディーゼル発電機からの電源だけで原子炉が正常を保っている危うさを認識していれば、さらに『ディーゼル発電機も故障するかもしれない』という『全電源喪失』を想定した予測計算をしたと思います。この計算も30分でできる。私がいた時はこのような先を読んだ予測計算も訓練でやっていた。原子力安全・保安院のERSS担当部署がそれをやらさなかったのではないか。この最初の津波が来るまでの1時間弱のロスが重大だったと思う」
──すべてが後手に回っているように思えます。なぜでしょう。
「何とか廃炉を避けたいと思ったのでしょう。原子炉を助けようとして、住民のことを忘れていた。太平洋戦争末期に軍部が『戦果を挙げてから降伏しよう』とずるずる戦争を長引かせて国民を犠牲にしたのと似ています」
──廃炉にすると、1炉あたり数兆円の損害が出ると聞きます。それでためらったのではないですか。
「1号機を廃炉する決心を早くすれば、まだコストは安かった。2、3号機は助かったかもしれない。1号機の水素爆発(12日)でがれきが飛び散り、放射能レベルが高かったため2、3号機に近づけなくなって14日と15日にメルトダウンを起こした。1号機に見切りをさっさとつけるべきだったのです」
──その計算がとっさにできるものですか。
「1号機は40年経った原子炉なのですから、そろそろ廃炉だと常識で分かっていたはずです。私が所長なら『どうせ廃炉にする予定だったんだから、住民に被曝させるくらいなら廃炉にしてもかまわない』と思うでしょう。1機1兆円です。逆に、被害が拡大して3機すべてが廃炉になり、数千人が被曝する賠償コストを考えると、どうですか? 私は10秒で計算します。普段から『老朽化し、かつシビアアクシデント対策が十分でない原子炉に何かあったら廃炉にしよう』と考えておかなければならない」
このままうやむやにすると、また同じことが起きる
私にとって不思議だったのは、これほど事故を予見し尽くしていた人材が電力業界内部にいたのに、その知見が無視され、死蔵されたことだ。松野さんにとっても、自分の長年の研究と専門知識が現実の事故対策に生かされなかったことは痛恨だった。
「私の言うことは誰も聞いてくれませんでした。誰も聞いてくれないので、家で妻に話しました。しかし妻にもうるさがられる。『私の代わりにハンガーにかけたセーターにでも話していなさい』と言うのです」
松野さんはそう言って笑う。
「このままうやむやにすると、また同じことが起きるでしょう」
「広島に原爆が落とされたとき、日本政府は空襲警報を出さなかった。『一矢報いてから』と講和の条件ばかり考えていたからです。長崎の2発目は避けることができたはずなのに、しなかった。国民が犠牲にされたんです」
「負けるかもしれない、と誰も言わないのなら(電力会社も)戦争中(の軍部)と同じです。負けたとき(=最悪の原発事故が起きたとき)の選択肢を用意しておくのが、私たち学者や技術者の仕事ではないですか」
そして、松野さんはさらに驚くような話を続けた。
そもそも、日本の原発周辺の避難計画は飾りにすぎない。国は原子炉設置許可の安全評価にあたって、格納容器が破損して放射性物質が漏れ出すような事故を想定していない。もしそれを想定したら、日本では原発の立地が不可能になってしまうからだ。
そんな逆立ちした論理が政府や電力業界を支配している、というのだ。
(次回に続く)』
長いので途中からです.全文は以下にあります.
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/35339
原子力発電そのものにリスクがあるのに、あえてそれを伏せてきた国の責任は大きいし,廃炉にしてもいいような古い原子炉を助けるために住民を犠牲にするような電力会社などこれからも信用するわけにはいかない.
それなのに再稼働に向けてまた補助金ばらまきをし,それを目当てに再稼働を受け入れようとする地方自治体がいまだに存在する.やっぱりこの国には原子力発電所を安全に運用する能力のある組織とか体制がもともと存在しないということだろう.